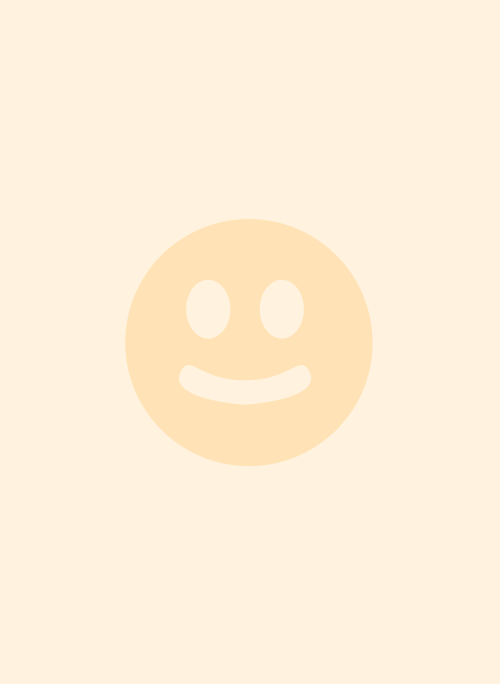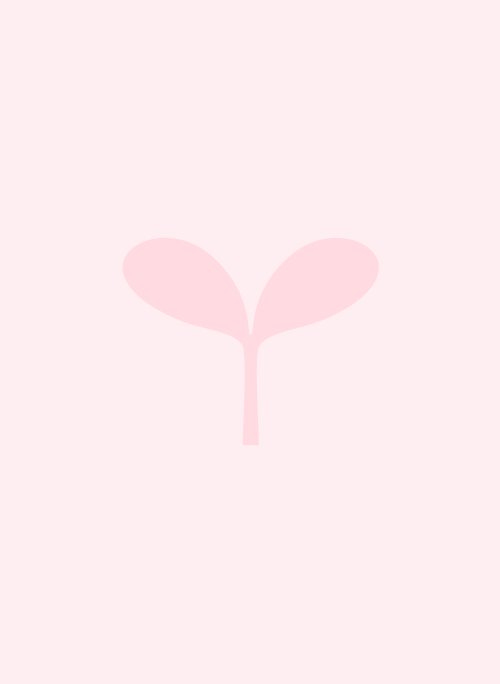まぁ、イイよ。
グズってようが、ソワソワしてようが。
『休み明けのコーヅキ先生は、ナニカにやたらとビビっている様子だった』
ソレさえ聞ければ、もうタケルに用はない。
「話してくれてありがと。
君ももう、帰れば」
「ちょっと待って!」
ハイ、解散、とばかりに立ち去ろうとした要の白い長袖シャツの袖を、小さな手が掴んで止めた。
見下ろせば、捨てられた子犬のように目を潤ませたタケルが。
その両隣には、泣かされちゃったタケルが気の毒になったのか、同じく捨てられた子犬のように目を潤ませたコージとユイが。
「なぁ、コーヅキ先生は悪くないだろ?
オレだって…
紫信に、ナニも悪いコトしてない…よな?」
「…」
ピクリと片眉を上げた要は、腕に縋りつくタケルから気まずそうに目を逸らした。
ナニコレ。
こーゆーの、苦手。
どーすりゃイイのかわからないから、とりあえず紛れもない事実だけを…
「あー… うん。
君たちは悪くない。
また図書館で君に会えたら、紫信もきっと喜ぶよ」
悪いのは、『アレ』ですから。
安心してヘニャっと笑ったタケルの頭を、要は骨ばった大きな手で恐る恐る撫でる。
そりゃあもう、ぎこちなく。
対人スキンシップとか、ほんっと苦手。