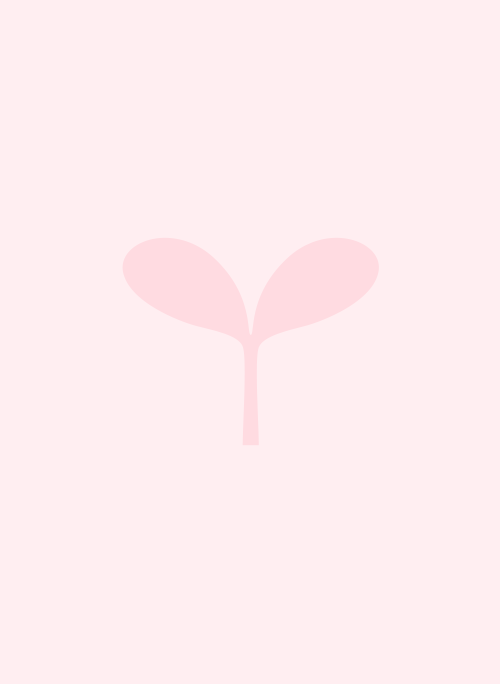マリアンヌはメイドに案内されて、木製のドアの前にいた。
メイドがノックし、ドアが開いた。そこは、クレモンセヌ家の一人娘のエリザベスの部屋であった。エリザベスは、部屋の中央の丸いテーブルに本と羽ペンを置いて座っていた。エリザベスは、ひらひらのフリルのついたドレスを着ていて、金色の巻き毛をした美女だった。
まるで、『不思議の国のアリス』のようね、とマリアンヌは思った。エリザベスはマリアンヌを見ると椅子から立ち上がり、片足をまげて、お辞儀した。マリアンヌもお辞儀した。
「はじめまして。こんにちは。私は、マリアンヌ・マクレーンと申します。今日からあなたの家庭教師をさせていただきます。よろしくね。」そういうと、マリアンヌはエリザベスを座らせ、自分も向かいの椅子に腰を下ろした。
メイドが一端下がり、二人のために紅茶とお菓子を持ってきた。
マリアンヌとエリザベスは、紅茶を飲んだ。
「先ほども紹介したけど、もう一度私のことを話すわ。私は、マリアンヌ・マクレーンよ。ミス・マクレーンと呼んでもらえればいいわ。年は25よ。週に2・3回来ることになっているの。今日は授業をせずに、これからの方針をきめていきたいわ。」
「確か、お母さまから伺った話だと、フランス語とラテン語を教えてほしいということだったわ。任せて!私、フランス語とラテン語は得意なの。」
すると、エリザベスが「できれば、幾何学も教えてほしいのですが。」と言ってきた。マリアンヌは、ギグっとして、身を固めた。幾何学!幾何学?!どうしよー、私、数学的なことは苦手だわ。教えられないと思う。自分でさえ、ガタガタなのに。ここは、断るべきね。
「申し上げにくいんだけど、幾何学は教えられないわ。あまり得意でないの。」そういうと、「少しだけでいいんです。簡単なことを習得しておきたいんです。」とエリザベスは言った。マリアンヌは、困ったわ、どうしたらいいの、と頭を悩ませた。そして、まあ何とかなるわっと思い、「分かったわ。あまり自信がないけど、がんばってみるわ。私も勉強するし。」そう言ってニコっとほほ笑んだ。それから二人は、これから授業をどう進めるか話を続けた。
マリアンヌは、自分の屋敷の自分の部屋に帰ってきて、フーっとため息をついた。
今日はクタクタだった。クレモンセヌ家は立派な屋敷だった。クレモンセヌ家が社交界の有名な家柄だとは、何となく知っていたけど、本当にその通りだった。我が家とは全然違うわ。それに、エリザベス嬢も気品があって、素晴らしかった。
将来は、相当の美人になりそうね。私、やっていけるかしら?うんうん、大丈夫。問題は、幾何学。本当に教えられるの?私。なんで、あんなこと言ってしまったのかしら。
学生時代、数学だけは満足いく点を取れなかったのに。しょうがないわ。多分、初めての仕事だから、かっこつけてしまったんだわ。
はあー。こうなったら、猛勉強するしかないわ。そう思うと、マリアンヌは、クローゼットの奥にしまってあった学生時代の古い数学の教科書を探しに行きました。
マリアンヌは、それから夜遅くまで机に向かう日々が続きました。
本当、教えるって大変なこと。学生時代より賢くなった気がするわ。
エリザベスに教えるために、予習を繰り返していました。エリザベスとは、年が近いこともあり、すぐに仲良くなりました。マリアンヌは、年下の妹たちがたくさんいたので、女同士の付き合いは得意でした。
エリザベスは一人っ子なので、マリアンヌを姉のように慕ってきました。そして、こんな姉がほしかったと言いました。エリザベスはかなり頭がいいので、教えるのは楽でした。
それでもエリザベスにとって苦手な幾何学には、マリアンヌは常に悪戦苦闘でした。今までは何とかエリザベスの質問に答えられていますが、果たしてこれからも大丈夫かどうか。
マリアンヌは、不安でたまらなくなりました。初めての仕事。失敗に終わらせたくないわ。何とかならないものかしら?
そうして、部屋の中をうろうろと歩き、窓の前で座り込んだマリアンヌは、ふとそう言えば、コスナー氏が、数学が得意だと言っていたことを思い出しました。
確か、国立取引所で働いているって。それなら、会計や財務管理は得意だろう。もしかして、彼に協力を仰いでもいいのかしら?忙しいかしら?でも、彼はこの間、また会いたいって言っていたし。家庭教師の仕事が忙しすぎて、すっかり忘れていたけど。聞いてみるだけなら、いいかもしれない。そう思って、マリアンヌは、書き物机から、紙と羽ペンを取り出し、サラサラと書きました。
「ミスター・コスナー
お忙しいところ、申し上げございません。あなたがお忙しいことは、十分に承知していますが、今回は頼み事があって、お手紙を差し上げることになりました。私が家庭教師の仕事に取り組んでいることは、ご承知でしょう。その事に付随して、困ったことが起きて、頭を悩ませているのです。私が数学が苦手だと申し上げたことを覚えていらっしゃられるか分かりませんが、そんな私が数学を教えることになったのです。ほとほとに困り果てておりまして、今まで何とか切り抜けてきたのですが、これからも続けられるか大変心配です。あなた様は、お得意だと話されておりました。もしお時間があれば、教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。厚かましいお願いだとは承知しております。どうかお許しください。もし気に食わなければ、お断りしていただいて構いません。
マリアンヌ・マクレーン」
ケヴィンは仕事から帰ってきて、ぐったりと疲れていた。今日の取引は最悪だった。鼻もちならない偉そうな貴族の議員が、己の利益のために要求を通そうとしていた。ケヴィンはなんとかうまくまとめようと苦心していたが、同僚が中々助けてくれなかった。結局、その貴族の要求の通りになっていった
。帰りにスラム街に寄ったが、そこも相変わらずだった。ケヴィンには、少しだけ仲が良い少年がいるのだが、彼とはよく話をしていた。名前はジョンと言って、年齢は10歳ぐらいだろうか。
本人もわからないらしい。何せ、孤児だし、物心ついた時から、一人でスラム街にいたそうだから。
ジョンは今は、仲間と共に靴磨きの仕事をしている。人懐っこい奴で、ここら辺では珍しくすぐにケヴィンと仲良くなった。
それからは、ケヴィンもよく彼に会いに来ていた。ジョンの住みかは、石がほとんど崩れ、むきだしだった。天井もあまりなかったので、雨でも降れば、家が水浸しになるだろう。
ジョンの廃墟で、ケヴィンはジョンと他愛もない話をしていた。今日の靴磨きの儲けは良かったなどという話題が出た。それから夜になってきたので、ケヴィンは帰ることにしようとした。ケヴィンが立ち上がると、ふと目に女性物のハンドバッグがあることに気付いた。ケヴィンはそのバックのところに行って、持ち上げてみた。「ジョン、これはどうした?」ジョンはそのカバンを見て、ギクッとした顔をした。「ああ、それ、ここら辺で落ちていたから拾ったやつだよ。中身は何にもなかった。盗んだわけじゃないからね。」といつもと違う声音で言った。ケヴィンはジーットハンドバッグを見た。ジョンの話は、おそらく嘘だろう。ジョンがソワソワして、早く話を切り上げたそうな様子からして、ジョンが盗んだものだろう。でも、追及するのはやめておこう。
「ふーん、そっか。じゃあ、このハンドバッグいらないよね。」ケヴィンが尋ねると、「ああ、いらないよ。あげるよ、ケヴィン。」そういうと、ジョンはケヴィンを廃墟から追い立てて、スラム街の方へ行こうとしました。そして、スラム街の外れまでケヴィンを送ってくれました。
「じゃあな。」そういうとジョンは、スラム街に戻っていきました。ケヴィンは、ハンドバッグをどうしたものかと思いつつ、家まで持って帰りました。
メイドがノックし、ドアが開いた。そこは、クレモンセヌ家の一人娘のエリザベスの部屋であった。エリザベスは、部屋の中央の丸いテーブルに本と羽ペンを置いて座っていた。エリザベスは、ひらひらのフリルのついたドレスを着ていて、金色の巻き毛をした美女だった。
まるで、『不思議の国のアリス』のようね、とマリアンヌは思った。エリザベスはマリアンヌを見ると椅子から立ち上がり、片足をまげて、お辞儀した。マリアンヌもお辞儀した。
「はじめまして。こんにちは。私は、マリアンヌ・マクレーンと申します。今日からあなたの家庭教師をさせていただきます。よろしくね。」そういうと、マリアンヌはエリザベスを座らせ、自分も向かいの椅子に腰を下ろした。
メイドが一端下がり、二人のために紅茶とお菓子を持ってきた。
マリアンヌとエリザベスは、紅茶を飲んだ。
「先ほども紹介したけど、もう一度私のことを話すわ。私は、マリアンヌ・マクレーンよ。ミス・マクレーンと呼んでもらえればいいわ。年は25よ。週に2・3回来ることになっているの。今日は授業をせずに、これからの方針をきめていきたいわ。」
「確か、お母さまから伺った話だと、フランス語とラテン語を教えてほしいということだったわ。任せて!私、フランス語とラテン語は得意なの。」
すると、エリザベスが「できれば、幾何学も教えてほしいのですが。」と言ってきた。マリアンヌは、ギグっとして、身を固めた。幾何学!幾何学?!どうしよー、私、数学的なことは苦手だわ。教えられないと思う。自分でさえ、ガタガタなのに。ここは、断るべきね。
「申し上げにくいんだけど、幾何学は教えられないわ。あまり得意でないの。」そういうと、「少しだけでいいんです。簡単なことを習得しておきたいんです。」とエリザベスは言った。マリアンヌは、困ったわ、どうしたらいいの、と頭を悩ませた。そして、まあ何とかなるわっと思い、「分かったわ。あまり自信がないけど、がんばってみるわ。私も勉強するし。」そう言ってニコっとほほ笑んだ。それから二人は、これから授業をどう進めるか話を続けた。
マリアンヌは、自分の屋敷の自分の部屋に帰ってきて、フーっとため息をついた。
今日はクタクタだった。クレモンセヌ家は立派な屋敷だった。クレモンセヌ家が社交界の有名な家柄だとは、何となく知っていたけど、本当にその通りだった。我が家とは全然違うわ。それに、エリザベス嬢も気品があって、素晴らしかった。
将来は、相当の美人になりそうね。私、やっていけるかしら?うんうん、大丈夫。問題は、幾何学。本当に教えられるの?私。なんで、あんなこと言ってしまったのかしら。
学生時代、数学だけは満足いく点を取れなかったのに。しょうがないわ。多分、初めての仕事だから、かっこつけてしまったんだわ。
はあー。こうなったら、猛勉強するしかないわ。そう思うと、マリアンヌは、クローゼットの奥にしまってあった学生時代の古い数学の教科書を探しに行きました。
マリアンヌは、それから夜遅くまで机に向かう日々が続きました。
本当、教えるって大変なこと。学生時代より賢くなった気がするわ。
エリザベスに教えるために、予習を繰り返していました。エリザベスとは、年が近いこともあり、すぐに仲良くなりました。マリアンヌは、年下の妹たちがたくさんいたので、女同士の付き合いは得意でした。
エリザベスは一人っ子なので、マリアンヌを姉のように慕ってきました。そして、こんな姉がほしかったと言いました。エリザベスはかなり頭がいいので、教えるのは楽でした。
それでもエリザベスにとって苦手な幾何学には、マリアンヌは常に悪戦苦闘でした。今までは何とかエリザベスの質問に答えられていますが、果たしてこれからも大丈夫かどうか。
マリアンヌは、不安でたまらなくなりました。初めての仕事。失敗に終わらせたくないわ。何とかならないものかしら?
そうして、部屋の中をうろうろと歩き、窓の前で座り込んだマリアンヌは、ふとそう言えば、コスナー氏が、数学が得意だと言っていたことを思い出しました。
確か、国立取引所で働いているって。それなら、会計や財務管理は得意だろう。もしかして、彼に協力を仰いでもいいのかしら?忙しいかしら?でも、彼はこの間、また会いたいって言っていたし。家庭教師の仕事が忙しすぎて、すっかり忘れていたけど。聞いてみるだけなら、いいかもしれない。そう思って、マリアンヌは、書き物机から、紙と羽ペンを取り出し、サラサラと書きました。
「ミスター・コスナー
お忙しいところ、申し上げございません。あなたがお忙しいことは、十分に承知していますが、今回は頼み事があって、お手紙を差し上げることになりました。私が家庭教師の仕事に取り組んでいることは、ご承知でしょう。その事に付随して、困ったことが起きて、頭を悩ませているのです。私が数学が苦手だと申し上げたことを覚えていらっしゃられるか分かりませんが、そんな私が数学を教えることになったのです。ほとほとに困り果てておりまして、今まで何とか切り抜けてきたのですが、これからも続けられるか大変心配です。あなた様は、お得意だと話されておりました。もしお時間があれば、教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。厚かましいお願いだとは承知しております。どうかお許しください。もし気に食わなければ、お断りしていただいて構いません。
マリアンヌ・マクレーン」
ケヴィンは仕事から帰ってきて、ぐったりと疲れていた。今日の取引は最悪だった。鼻もちならない偉そうな貴族の議員が、己の利益のために要求を通そうとしていた。ケヴィンはなんとかうまくまとめようと苦心していたが、同僚が中々助けてくれなかった。結局、その貴族の要求の通りになっていった
。帰りにスラム街に寄ったが、そこも相変わらずだった。ケヴィンには、少しだけ仲が良い少年がいるのだが、彼とはよく話をしていた。名前はジョンと言って、年齢は10歳ぐらいだろうか。
本人もわからないらしい。何せ、孤児だし、物心ついた時から、一人でスラム街にいたそうだから。
ジョンは今は、仲間と共に靴磨きの仕事をしている。人懐っこい奴で、ここら辺では珍しくすぐにケヴィンと仲良くなった。
それからは、ケヴィンもよく彼に会いに来ていた。ジョンの住みかは、石がほとんど崩れ、むきだしだった。天井もあまりなかったので、雨でも降れば、家が水浸しになるだろう。
ジョンの廃墟で、ケヴィンはジョンと他愛もない話をしていた。今日の靴磨きの儲けは良かったなどという話題が出た。それから夜になってきたので、ケヴィンは帰ることにしようとした。ケヴィンが立ち上がると、ふと目に女性物のハンドバッグがあることに気付いた。ケヴィンはそのバックのところに行って、持ち上げてみた。「ジョン、これはどうした?」ジョンはそのカバンを見て、ギクッとした顔をした。「ああ、それ、ここら辺で落ちていたから拾ったやつだよ。中身は何にもなかった。盗んだわけじゃないからね。」といつもと違う声音で言った。ケヴィンはジーットハンドバッグを見た。ジョンの話は、おそらく嘘だろう。ジョンがソワソワして、早く話を切り上げたそうな様子からして、ジョンが盗んだものだろう。でも、追及するのはやめておこう。
「ふーん、そっか。じゃあ、このハンドバッグいらないよね。」ケヴィンが尋ねると、「ああ、いらないよ。あげるよ、ケヴィン。」そういうと、ジョンはケヴィンを廃墟から追い立てて、スラム街の方へ行こうとしました。そして、スラム街の外れまでケヴィンを送ってくれました。
「じゃあな。」そういうとジョンは、スラム街に戻っていきました。ケヴィンは、ハンドバッグをどうしたものかと思いつつ、家まで持って帰りました。