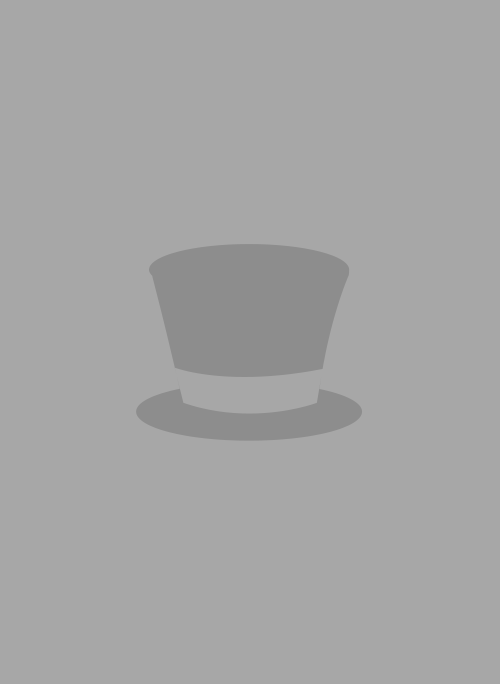その言葉に、私が初めて抱いた感情は何だったのだろう。一度に飛び出した感情が多すぎて、どれがメインなのかも、どれが最初のものなのかも、どれが私の本当の気持ちなのかも分からずにいた。
「もちろん私達だけの予想だから、多分違うと思うんだけど…」
「でもそう考えたら、辻褄が合う気がするの」
どういうこと? そう尋ねる間もなく、二人は持論の補填を開始した。
「先生は、その好きだった人と、詩音を重ねてるんだと思う」
「ほら、詩音って昔、図書委員やってました~って感じが出てるじゃん? まぁ、アタシ達が詩音の過去を知ってるからそう感じるだけなのかもしれないけど…」
確かに、あれだけの読書量をこなしてきた私だ。体から本のオーラが滲み出ていたとしても、そこまで不思議ではない。
「それに、私達聞いちゃったんだ」
「…聞いた…?」
「うん。…演劇部、もしかしたら潰れてたかもしれないって話」
その後の話は少し長くなるのでまとめてみる。
両里高校の部活は、部活ごとに定められた一定の人数が入部届を出して部員として登録されていないと、その部活が維持できないというシステムになっているらしい。演劇部の「最低人数」は五人。つまり、私達の学年で入部する人が一人もいなかったら、演劇部はなくなっていたかもしれないというのだ。
「…顧問をしてる尾張先生にとっても、演劇部がなくなるのは嫌なことだもん」
「だから、廃部の危機を救った私達五人には、きっとただの教え子以上の、特別な感情があるんじゃないかな」
それらが、私に対する恋愛感情となって表に現れたというのか…。
「…まぁまぁ、繰り返すようだけど、あくまで予想だから」
「そんなに気にしすぎなくてもいいんじゃない? 身が持たないし」
…そうかもしれない。私はずっと、二人の話をそういうスタンスで聞いていた。二人もきっと、そういうつもりで話していたのだろう。
だけど、一つだけ言えることがあるとすれば。
…先生が私のことを好きでいるのは、嫌じゃない、ということだ。
「もちろん私達だけの予想だから、多分違うと思うんだけど…」
「でもそう考えたら、辻褄が合う気がするの」
どういうこと? そう尋ねる間もなく、二人は持論の補填を開始した。
「先生は、その好きだった人と、詩音を重ねてるんだと思う」
「ほら、詩音って昔、図書委員やってました~って感じが出てるじゃん? まぁ、アタシ達が詩音の過去を知ってるからそう感じるだけなのかもしれないけど…」
確かに、あれだけの読書量をこなしてきた私だ。体から本のオーラが滲み出ていたとしても、そこまで不思議ではない。
「それに、私達聞いちゃったんだ」
「…聞いた…?」
「うん。…演劇部、もしかしたら潰れてたかもしれないって話」
その後の話は少し長くなるのでまとめてみる。
両里高校の部活は、部活ごとに定められた一定の人数が入部届を出して部員として登録されていないと、その部活が維持できないというシステムになっているらしい。演劇部の「最低人数」は五人。つまり、私達の学年で入部する人が一人もいなかったら、演劇部はなくなっていたかもしれないというのだ。
「…顧問をしてる尾張先生にとっても、演劇部がなくなるのは嫌なことだもん」
「だから、廃部の危機を救った私達五人には、きっとただの教え子以上の、特別な感情があるんじゃないかな」
それらが、私に対する恋愛感情となって表に現れたというのか…。
「…まぁまぁ、繰り返すようだけど、あくまで予想だから」
「そんなに気にしすぎなくてもいいんじゃない? 身が持たないし」
…そうかもしれない。私はずっと、二人の話をそういうスタンスで聞いていた。二人もきっと、そういうつもりで話していたのだろう。
だけど、一つだけ言えることがあるとすれば。
…先生が私のことを好きでいるのは、嫌じゃない、ということだ。