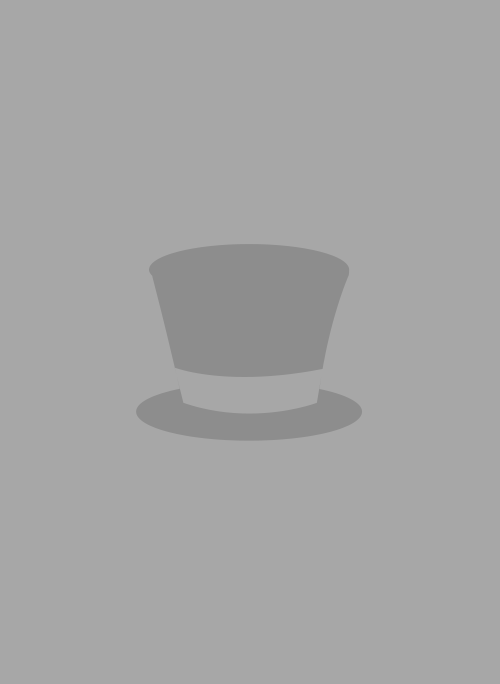そして、部活が終わった。
「津田さん、ちょっと」
呼び出したのは、先生の方だった。
「…朝の話なんだけどね」
夜の体育館裏。星と電気の光が交錯する空気に、先生の声がブレンドされる。
「…僕があの時いなくなったのは、見回りだったからなんかじゃないんだ。もっと…ちっちゃい理由」
「ちっちゃい理由…?」
「うん。教師ならそんな理由で抜けちゃいけない、小さな小さな、些細な理由」
先生は一度、ゆっくりまぶたを閉じ、そしてもう一度開いた。
「…見たくなかったんだ…津田さんの泣いてる顔が」
「…えっ…?」
理由の中に私の名前が出てくるなんて、誰が想像できただろうか。
「津田さんの泣き顔を、見たくなかったんだ。ただそれだけの、些細な理由」
「…それで…あそこにおらんくなったんですか…?」
「うん…」
力なくうなずく先生は、もうどこにも置くことができない申し訳なさを全身に負っていた。
「僕、弱虫だから。絶対いなきゃいけないのに、僕一人の些細な気持ちで、逃げたんだ」
逃げた。それを正直に言えている分、私よりマシだ。私が最初に抱いた感情は、怒りでも呆れでもなく、それだった。
「…何で…ウチの泣いてる顔を見たくないって思ったんですか…? ウチ以外にも泣いてる人はめっちゃいましたけど…」
「津田さんが」
私の言葉を遮った割に、その後の言葉はそう簡単には出てこなかった。
「…いや、特に明確な理由はないかな。ただ他の子より、見たくない涙だった。それだけ」
先生が何かを隠しているのは分かっていた。けれどもそれを問い詰める勇気も技術も、私は持ち合わせていなかった。
「津田さん、ちょっと」
呼び出したのは、先生の方だった。
「…朝の話なんだけどね」
夜の体育館裏。星と電気の光が交錯する空気に、先生の声がブレンドされる。
「…僕があの時いなくなったのは、見回りだったからなんかじゃないんだ。もっと…ちっちゃい理由」
「ちっちゃい理由…?」
「うん。教師ならそんな理由で抜けちゃいけない、小さな小さな、些細な理由」
先生は一度、ゆっくりまぶたを閉じ、そしてもう一度開いた。
「…見たくなかったんだ…津田さんの泣いてる顔が」
「…えっ…?」
理由の中に私の名前が出てくるなんて、誰が想像できただろうか。
「津田さんの泣き顔を、見たくなかったんだ。ただそれだけの、些細な理由」
「…それで…あそこにおらんくなったんですか…?」
「うん…」
力なくうなずく先生は、もうどこにも置くことができない申し訳なさを全身に負っていた。
「僕、弱虫だから。絶対いなきゃいけないのに、僕一人の些細な気持ちで、逃げたんだ」
逃げた。それを正直に言えている分、私よりマシだ。私が最初に抱いた感情は、怒りでも呆れでもなく、それだった。
「…何で…ウチの泣いてる顔を見たくないって思ったんですか…? ウチ以外にも泣いてる人はめっちゃいましたけど…」
「津田さんが」
私の言葉を遮った割に、その後の言葉はそう簡単には出てこなかった。
「…いや、特に明確な理由はないかな。ただ他の子より、見たくない涙だった。それだけ」
先生が何かを隠しているのは分かっていた。けれどもそれを問い詰める勇気も技術も、私は持ち合わせていなかった。