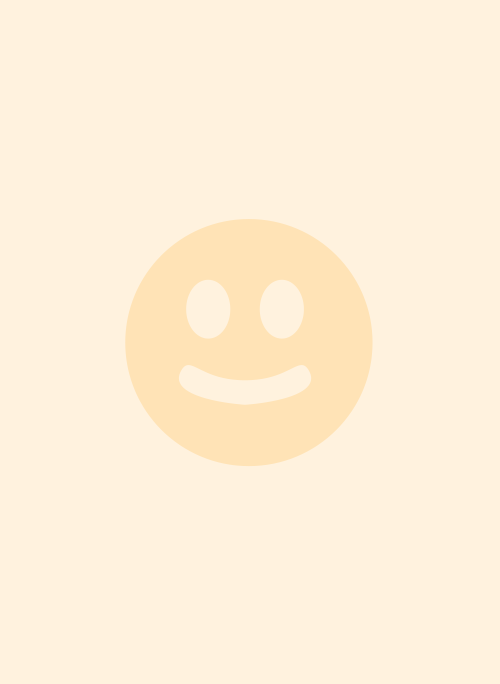僕は出来るだけ彼女と話をするために、最初の偶然を自分のものにしたくて、いつでも混雑する電車の列の最後尾に並んでいる。だけど彼女はその時々によって列の前にいたりとか真ん中だったりするので、鞄がぶつかるというハッピーな偶然は滅多に生まれなかった。
イライラして焦るような、不思議な感覚。自分でもどうしたいかが判らなかった。声をかけよう、と考えることもあったけれど、一体何ていえばいいんだ?と悩んでは寸前で上げかけた手を下ろしてしまう。
恋をしたことはある。
だけど、こんなのは初めてだった。
こんな、最初の会話のきっかけですら困ってしまう、そんな淡い恋は。
季節が変わって、秋になっていた。
僕は今日もホームへ足取り軽く上がっていく。
僕の毎日は、この朝の一瞬のためにあるようなものなのだ。この朝の混雑するホームであの人を見る楽しみが終わってしまうと、あとはただの日常がだらだら~っと続くだけなのだから。帰りの電車でも探してはみたけれど、一度も会えたことはないから退勤時間が違うのだろうって思っていた。だから朝が勝負なのだ。
今日も目で彼女を探す。いつもの車両、いつもの立ち位置。・・・あ、いた。
つい口元がゆるむのを感じながら僕は緊張して歩いていく。今日はあの人は、列の最後に並んでいる。もしかしたらあの偶然がきたのかも。もしかしたら────────
ふ、と、あの人が顔を上げて僕を見た。
バッチリと目が会う。
え?僕は一瞬驚いてしまう。
だって、あの人が、ふんわりと微笑んで会釈してくれたからだ。