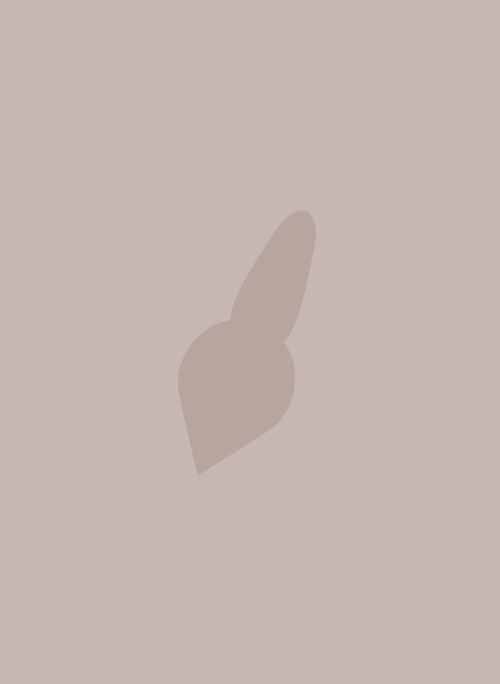「...でも、よく紫陽花の花言葉知ってたね?」
そう言えば、彼は、"それは、名前が..."なんて、小さくなっていく声に、なんだか可笑しくて、笑った。
そして、いつの間にか、もうすぐそこに私の家が見えてくる。
「...傘、一緒にいれてくれて、
あと、家まで送ってくれて、ありがとう」
「ううん」
「幸雨くんって、優しいね」
私のそんな言葉に、彼からの返事がない。表情を窺おうとしても、彼の顔は傘で隠れていて、上手く見えない。
どうしたのかと、声を掛けようとした時。彼と目が合う。その目はどこか熱を持っているように見えた。
「.....俺は、誰にでも優しい訳じゃないよ」
「......え?」
「じゃあ、またね」
"紫陽"
と私の名前を小さく囁いて、踵を返す彼。取り残された私は、静かに胸が高鳴った。
あの人は、"紫陽"と私の名前を
呼んだことがあっただろうか。
そんなことを思いながら、
私は彼の背中を見ていた。
*end*