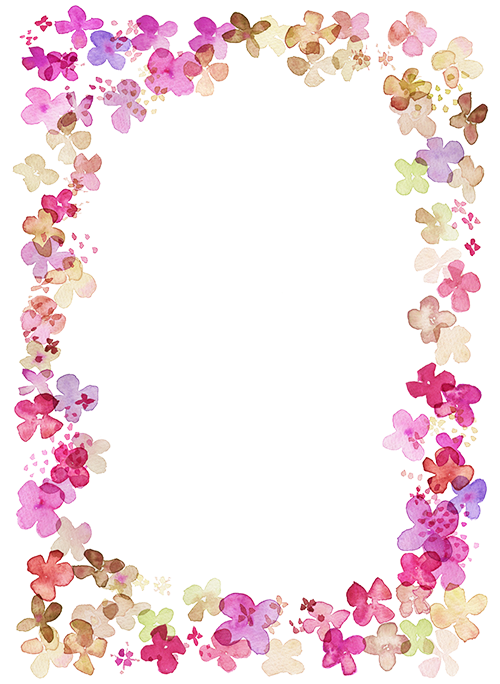駐車場まで向かう薄暗い道を、エリーと手を繋いだまま歩く。
なんでこの手、離されないんだろう。どこで離れるんだろう。
心が震える。エリーの横顔を見れなくて、ただ足元を辿る。
『飲み直すって、焼き鳥屋さんに行くの?』
「うん。藤澤、あんま食べてないだろ?」
『そんなことないよ?エリーがお肉持って来てくれてたし。
まぁ、まだ食べれるかなっていう気はするけど。エリーの方が、焼くばっかりで食べれなかったんじゃない?』
暗い雑木林。こんなシチュエーションでエリーと二人、手を繋いで。
なんだか現実じゃないみたい。
「それはいいんだけどさ、あいつらに藤澤のことばっか聞かれて。そっちの相手の方が大変だったよ。笑」
エリーと“いたしてる”かを揶揄いに来た、マルコメ少年を思い出した。
『そっか・・・。汗
なんであの子たち、この話知ってたんだろう?あの、佐伯さん?っていう方が話したのかな?』
「あ、俺が言った。藤澤のこと、彼女だって。」
あっさり放たれたエリーの返しに、耳を疑う。
『は?!なんで?!なんであの子たちにも言ったの?!』
「みんなに、藤澤に俺の彼女として接して欲しかったから。」
なんで?!そう返そうとしたら、エリーが立ち止まる。
ジンジン鳴る左手が、込められた力のせいか熱のせいなのか分からない。
エリーの瞳に射抜かれる。夜闇の中で、黒く光る。
自分の喉が鳴る音が聞こえた。
「こういう感じだよ。」
木々の間を流れて行く風の音。
熱を持った首筋を、春の夜が駆け抜けて行く。
「俺と付き合ったら、こういう感じだよ。」
瞬間、ばらばらと解けていく記憶。
蘇るワンシーン。
“全く想像ができないの”
“柊介さん以外と付き合う自分が、想像できないってことか”
“なるほどね”
エリーの目論見が、その正体を明かす。
エリーが今日教えたかったのは、きっとサッカーのルールなんかじゃない。
優しさが痛い。思い遣りが痛い。
気づかなかった、自分が痛い。
『エリー・・・』
「もう誰かを好きになれないなんてこと、ないから。
失いたての時は、誰だってそう思うよ。その気持ちはよく分かる。」
泣きそう。この期に及んで、まだ甘えが残ってる。
「だけど藤澤なら、何度でも誰とでもちゃんと恋愛出来るから。」
息を吐いたら涙が溢れそうで、唇を噛んだ。
「俺が保証する。だから頼むから___」
それなのに頬は、温かく濡れた。
「自分が幸せになれる道を選んで。」
エリーの情には、友情とか愛情とか、そんな境がないのかも。
だってこんなに温かくて、こんなに親身で。
私はエリーの思惑通り、ちゃんと今日1日エリーと恋愛してるかのような気分になれた。
柊介以外の人でも、ちゃんとドキドキして楽しくて。
エリーが彼氏だという響きが眩しかった。
私を見つめる穏やかな視線に、安堵する心は蕩けた。
女の下心なんてくだらない。
逃れられないのは、私の弱さだ。
もしも柊介を選ぶなら、ちゃんとそれ以外の理由を。
柊介の過ちもズルさも、未来に残る傷痕も。
あの人に纏わる何もかもを、受け入れる覚悟を。
声をあげて泣く私の手を、エリーはただ強く握ってくれていた。
彼の体温に心が浄化されて、悪いものが全部涙として出ていっているような気がした。
見上げる月は、細く細く欠けていて。
今夜は頼りないけど、そこにはこれから満ちていく強さも香っていた。