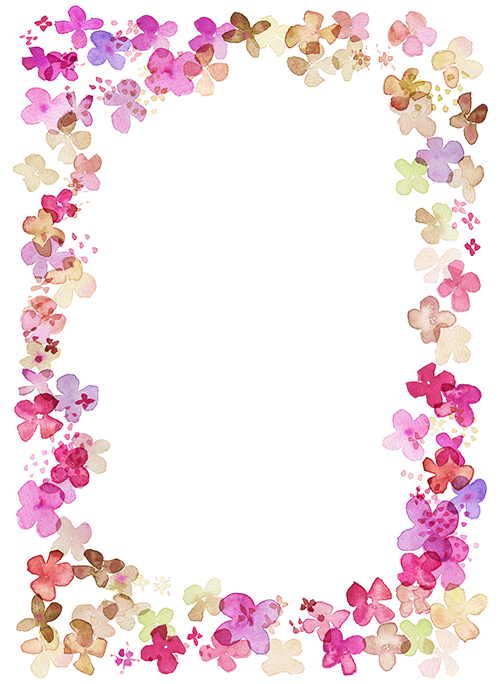昨夜の後味 _ 2
「家、どこ。」
タクシーのドアに手をかけて、シートに沈んだ私を見下ろす。
あれだけのキスをしておきながら、八坂蒼甫は本来の役割を務めたがるエレベーターを降りた後。
あっさり私を、タクシーに押し込んだ。
『か、帰るの?』
このまま、一人で?
「帰れよ。」
驚いて見上げれば、逆に驚いたように即答された。
「だから、家の住所。」
彼の視線が、ふわっと運転席に泳ぐ。
下を向いて、きっともう殆ど色の残っていない唇を噛んだ。
一人で帰りたくない。
あの家にいたら、柊介が来るかもしれない。
だけどそんな事、初めて言葉を交わすこの人になんて言えない。
バッグミラーの中からと、すぐ左手頭上からと。
双方からイラついた視線を感じるのに、言葉が出て来ない。身体が、竦んだ。
「…おい、」
業を煮やした彼が覗き込んだその時、涙が溢れた。
情け無い。
何やってるの、ほんとに、私。
彼に何を期待したんだろう。
この悪夢みたいな夜を、変えてくれるとでも思ったのかな。
帰ろう、一人で。
私があのレストランに行かなければ、きっと柊介は家に来る。
心配したような、顔をして。あの甘い声で、私の名前を呼んで。
そして私たちは。
今日、終わるんだ_________
「赤坂まで。」
左肩を押されるような感覚に顔を上げた時。
タクシーはドアを閉めるのと同時に、走り出した。
『え?ええっ?!』
うち、赤坂じゃないけど!
私を押し退けるように乗車してきた八坂蒼甫は、長い脚を窮屈そうに組み直すと。
上質な革の鞄から取り出した携帯を、平然と弄りだす。
『いやいやいや、え、ていうか、赤坂って何?!今どこに向かってるの?!』
「うち。」
『…は?』
「だから、俺んち。」
『な、ん、で…?』
「帰るんだよ。」
彼の悠長な横顔と対比して、やけにスピードを上げて流れる、窓の外の景色に慌てる。
『いや、ちょ、あた、あたしはっ?』
「来る?」
『は?!な、なんで?!』
急展開すぎる、この場面に。乾いた唇がパクパク鳴って、まともな言葉が出てこない。
ふと、携帯の画面から顔を上げた彼は。
一瞬、眉を寄せて何かを思い出そうとしているような表情を見せた後__________
私を振り返って、ただ一言、こう言った。
「拾って欲しそうな、顔してたから?」