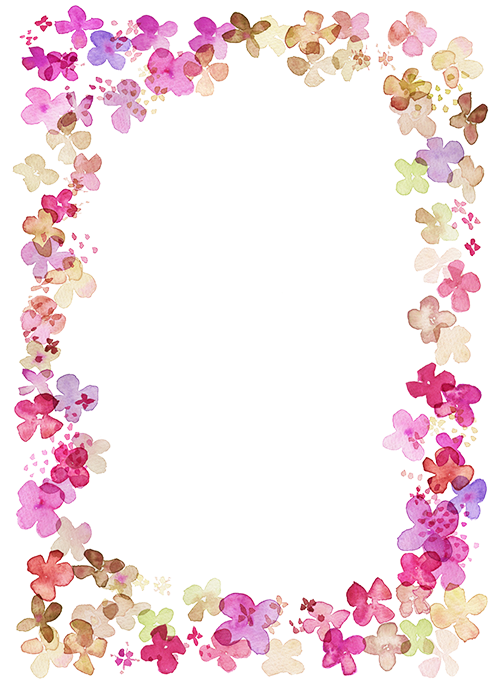昨夜の後味 _ 1
昼休みになると同時に、鼻穴を膨らませながら近づいて来た眞子に首を振ると。
驚いたように、目を剥いた。
「まじで?違ったの?なんで?まだって?」
華奢な手が握りしめる、2つのコーヒー缶。
これから屋上で、“甘やかな報告”を受けると信じて疑わない、ピンク色の頬。
罪悪感に似た息苦しさを感じて、眞子のその全てから目を反らす。
ミニバッグを手に、立ち上がった。
『ランチ行こ、普通に。お腹空いちゃった。』
「…十和、何かあった?」
顔を上げたら、泣くかも。
それでも顔を上げて首を振ると、眞子の瞳は笑みを失くした。
「…外、出よっか。ブルーノート行こ。」
『ありがとう。』
お財布取ってくる、と。
踵を返す瞬間、肩に触れた眞子の手は小さくて。
昨夜、私を押さえ付けた大きな掌が甦って。
唇は、疼いた。
ブルーノート。
本と音楽に囲まれた、不思議な地下空間。
私たちの報告会は、いつもこのカフェの、一番左奥のソファ席で。
大好きなスモークサーモンのサラダランチなら、と思ったのに。
その僅かな匂いにも吐き気を感じた自分に、驚いた。
「それから?連絡は?すっぽかしたんでしょう、オーベルジュのディナーも。」
『…分かんない。携帯の電源、切ってたから。』
「清宮さん、家には来なかったの?」
『…分かんない。』
「は?」
『寝ちゃったの、帰ったらすぐ。なんかすごい、疲れちゃって。』
オレンジ色のクリームチーズに、無意味にフォークを突き刺した。
何て言えばいいのか、分からない。
あのキスは夢だったんじゃないかと思う。それくらい、今でも事態が掴めていない。
「なるほどね、あまりの事態に、帰ったら疲れ果てて寝てしまったと。」
『そうそう。』
だけどこういう時、眞子は。
「で?」
『で?』
「その浮気現場目撃から、家に帰ってからの爆睡まで。
あんたをそんなに疲れさせる、何があったの?」
鋭い嗅覚で、絶対に的を外さない。