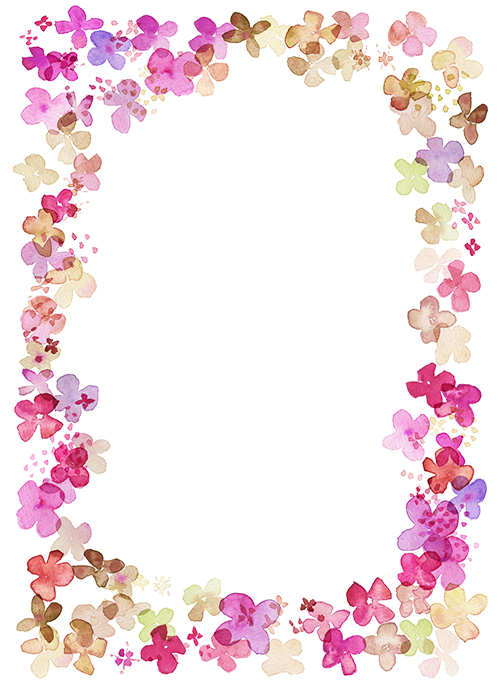昨夜の後味 _ 6
もう何度目かで、辿る彼のキス。
あれはきっと乱暴、だったのに。
今となっては、なぜか真っ青な海が浮かんだ。
果てないコバルトブルーへ、真後ろに突き落とされるような。
あのキスには、そういうスリルと清涼が潜んでた。
ポーチから、ビューラーが音を立てて洗面台に溢れ落ちて。慌てて拾い上げる。
「ちょっとー、うっとりしないでよー。」
『してない!笑』
弾けた笑顔の眞子の口元から、小さな八重歯が覗いた。
よかった、私の親友はちゃんと眞子で。
眞子は、出会った日から何度だって私にそう思わせる。
突きつけられた現実は、未だどうにも動いてはいないけれど。
驚くほど軽くなった気持ちを確かめながら、並んで女子トイレを後にした。
「え、あんたまだ携帯の電源入れてないの!?」
『うん。話したくないんだもん。話すこともないし。』
「やばいって!清宮さん絶対死ぬほど連絡して来てるって。すっぽかしたままはやばいよ。いや、すっぽかして良かったんだけどね。
あー、でも来るよ、秘書課まで!」
『来ないよ。今日は大阪出張だもん。』
「そういう問題じゃ…!じゃあ明日来るかもしれないでしょう?!」
眞子は、柊介が秘書課にやって来て。
私に対して騒ぐんじゃないかと心配してる。
だけど柊介は、そんなヘマをするような男じゃない。
社内恋愛を隠していたわけじゃないけれど。
堂々、手を繋いで新宿を歩いたりもしたけれど。
後日、後輩女子たちに取り囲まれて尋問されれば、「見間違いじゃない?」と。
「俺と藤澤さんの手、本当に繋がってた?」と。
鉄壁の微笑みと甘い声色で、有無を言わせず黙らせる。
かと思えば、私が男の先輩に誘われているようなシーンでは。
当たり前のように割入ってきて、「今日は遅くなりそう?」と髪を撫でる。
そう、柊介は。
“認めないけど、隠さない”
女子を納得させる社内恋愛の模範解答みたいな、スマートなやり方だった。
…だった、って。
私、柊介と別れるのかな。
どうしたいんだろう、私。
確かにいつまでも。逃げてるわけにはいかない。
もうそろそろ秘書課に着いて、私が逃げそうなことを察知した眞子が。
口調にラストスパートをかけてきた、その時。
「エリー!!」
縋るようにあげた声に、思わず顔を上げた。