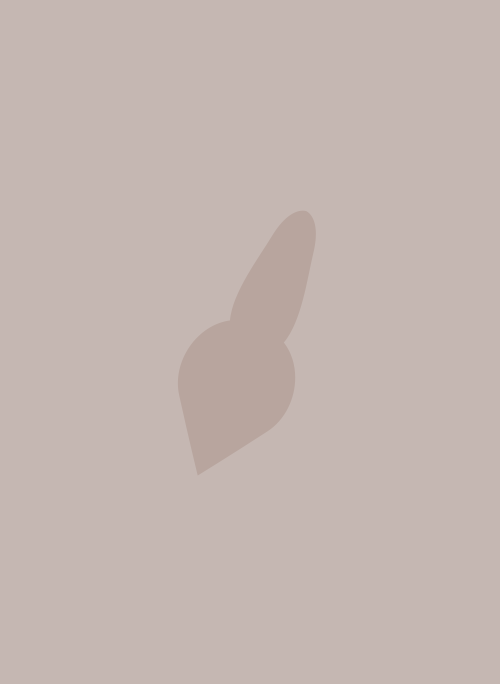春の花と草木の香りを運ぶ風が鼻をなでる。
「驚いたわ。セザル。私も同じことを考えていたわ。少し前のあの日、ラプラムルの姫の追悼式で上げられていた煙を見た日から。だからあのあと教会に行って私も本を読んだわ。」
「…え?お前も、か!それで、何か面白いことが書いてあったか?」
「ううん。何も大したことは。……あ、けれどひとつだけ……」
これは、サゼルには言ってもいいだろうか。ううん。秘密にする必要だってないわね。
わたしは、読んだ本に挟まっていた、姫であろう赤子の写真のことを話した。
話しているうちに、サゼルの瞳が爛々と輝き出すのがわかった。
「やっぱり!セゼリア!きっと……いやちがう、絶対に、そうだ。……姫はきっと生きているよ!」
「……へっ!?、、」
サゼルがあまりにも頓珍漢なことをいうからびっくりした。
「おかしいわよ。サゼル。あかちゃんが載せられたのは箱のような脆い船なんでしょう?ラプラムル近海の海流に耐えられるわけがないわ。」
「だろうね。 けどもし、姫を陸まで運んだヤツがいたら?」
「船が箱に近づいたら陸にいた市民や王様たちが気づくわ。」
「船なら。でも、飛べるモノだったら。……例えば、カラスやフクロウみたいに。」
「……!」
私は、鼓動が高まっているのを感じた。
思いつきもしなかった。
有り得ないことだろうに、なぜか、すっと腑に落ちた。
カラスやフクロウが近くの陸地まで箱舟を引っ張っていけば、確かに姫は助かっているのかもしれない。
ふと、何か心の中で感情が蠢くのを感じた。もやもやするような、胸を締め付けるような、激しい旋律に掻き立てられるような感覚が。
しばらく途方に暮れていたが、満足に満ち溢れたような顔のサゼルにまた手を引かれて、おばさまの待つ家まで送り届けられた。
「送ってくれてありがとう、サゼル。またお菓子を焼いたら持っていくわね。」
「こちらこそ、たまごありがとう。ラプラムルのこと、もう少し詳しく調べてみるよ。それじゃあ。」
鼻歌しながら去っていくサゼルを見送ると、私は家に入った。
外に見ていた者がいるなんてことに気づかずに。
“大キクナッタネ。モウスコシシタラ………楽シミニシテイルヨ”
大きな羽音が響いた。