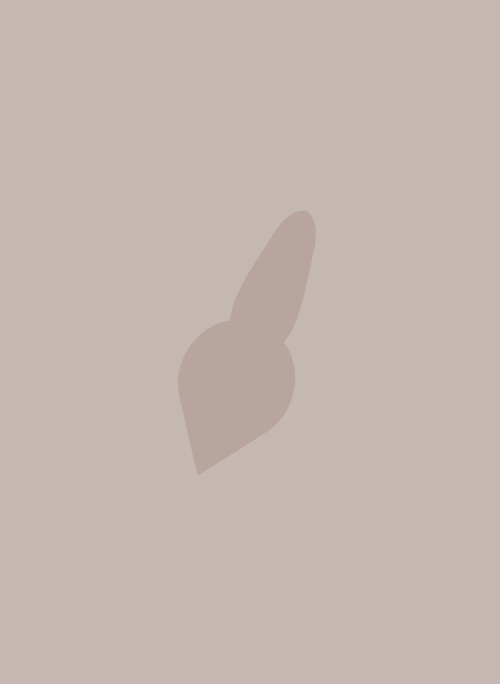「神崎、お疲れ様」
「……ああ、もうこんな時間か」
「うん、そうなんだよね。今日はかなり切り上げるの遅くなっちゃって」
「……別にそれは構わないが、なんでそんなに挙動不審なんだ?」
「えっ!?そ、そんなことは、ない、よ…」
「どこがだよ。例の桐川か?」
「桐野、ね?桐野さん」
「例の桐野か?」
「…わざわざ言い直さなくていいから、」
明日の軽食の下拵えをとっくに終わらせていた神崎は、食材の点検すらも全て終わらせ、あまつさえ包丁を研いでいた。
僕が勤務終了を伝えに来るまで延々と己のフィールドに引きこもり続けるのは昔から変わらない。
頼むから可笑しいと気付いてくれよ。寧ろ時計を見るのを習慣付けてくれ。
神崎律。
僕が中学の時からの同級生で良き理解者だ。
元々彼の両親が飲食店を営んでいたお陰か、料理のセンスは当時からずば抜けていた。バレンタイン前の実習等では、なぜか女子達はあげるのではなく、神崎の手作り料理やお菓子を手に入れようと躍起になっていた。
そんな神崎に喫茶店の話をしたのがこの[徒然草]の始まりだったりするのだが、今はそんな事にしみじみと思い耽っている場合ではない。
「神崎、助けて」
「まさかお前、発注間違えたのか?殺すぞ」
「ちがっ、桐野さん、が」
「…桐野が?」
「桐野さん、を、家まで送らなきゃ、いけなくて」
「……それで?」
「どうしよう、神崎……!」
「中学生か」
「か、神崎も、一緒に、」
「……一応聞くだけ聞くが、せめて中間地点の病院辺りか?」
「…………公園方面、かな」
「真逆じゃねえか、頑張れよ」
「神崎いいいい」
食器の洗い残しや、掃除がすみずみまで行き届いているかをざっと見渡して確認した神崎は、そのままキッチンを出て僕をすり抜けて控え室へと向かう。
そんな彼のマイペースさにはとっくに慣れている。中学生の頃からそうだったからだ。
マイペース。だが、他人を思い遣る心は人一倍。
人が傷付く事に関しては、とても敏感な奴だと僕は思う。
神崎に続いて控え室に入ると、桐野さんは既に着替えを終えていたようで席を外していた。
唯くん曰く、軽くメイクを直して来るのでは、との事だ。女性は大変だなあとつくづく感じる。
高校生ぐらいまではメイクはして来るなと指導され、社会人になればせめてファンデーションぐらいはして来いと上司に注意を受ける。
世の中理不尽だと、結局そうなるならメイクの基礎ぐらい教えて欲しかったと姉が文句を言っていた。
「……ああ、もうこんな時間か」
「うん、そうなんだよね。今日はかなり切り上げるの遅くなっちゃって」
「……別にそれは構わないが、なんでそんなに挙動不審なんだ?」
「えっ!?そ、そんなことは、ない、よ…」
「どこがだよ。例の桐川か?」
「桐野、ね?桐野さん」
「例の桐野か?」
「…わざわざ言い直さなくていいから、」
明日の軽食の下拵えをとっくに終わらせていた神崎は、食材の点検すらも全て終わらせ、あまつさえ包丁を研いでいた。
僕が勤務終了を伝えに来るまで延々と己のフィールドに引きこもり続けるのは昔から変わらない。
頼むから可笑しいと気付いてくれよ。寧ろ時計を見るのを習慣付けてくれ。
神崎律。
僕が中学の時からの同級生で良き理解者だ。
元々彼の両親が飲食店を営んでいたお陰か、料理のセンスは当時からずば抜けていた。バレンタイン前の実習等では、なぜか女子達はあげるのではなく、神崎の手作り料理やお菓子を手に入れようと躍起になっていた。
そんな神崎に喫茶店の話をしたのがこの[徒然草]の始まりだったりするのだが、今はそんな事にしみじみと思い耽っている場合ではない。
「神崎、助けて」
「まさかお前、発注間違えたのか?殺すぞ」
「ちがっ、桐野さん、が」
「…桐野が?」
「桐野さん、を、家まで送らなきゃ、いけなくて」
「……それで?」
「どうしよう、神崎……!」
「中学生か」
「か、神崎も、一緒に、」
「……一応聞くだけ聞くが、せめて中間地点の病院辺りか?」
「…………公園方面、かな」
「真逆じゃねえか、頑張れよ」
「神崎いいいい」
食器の洗い残しや、掃除がすみずみまで行き届いているかをざっと見渡して確認した神崎は、そのままキッチンを出て僕をすり抜けて控え室へと向かう。
そんな彼のマイペースさにはとっくに慣れている。中学生の頃からそうだったからだ。
マイペース。だが、他人を思い遣る心は人一倍。
人が傷付く事に関しては、とても敏感な奴だと僕は思う。
神崎に続いて控え室に入ると、桐野さんは既に着替えを終えていたようで席を外していた。
唯くん曰く、軽くメイクを直して来るのでは、との事だ。女性は大変だなあとつくづく感じる。
高校生ぐらいまではメイクはして来るなと指導され、社会人になればせめてファンデーションぐらいはして来いと上司に注意を受ける。
世の中理不尽だと、結局そうなるならメイクの基礎ぐらい教えて欲しかったと姉が文句を言っていた。