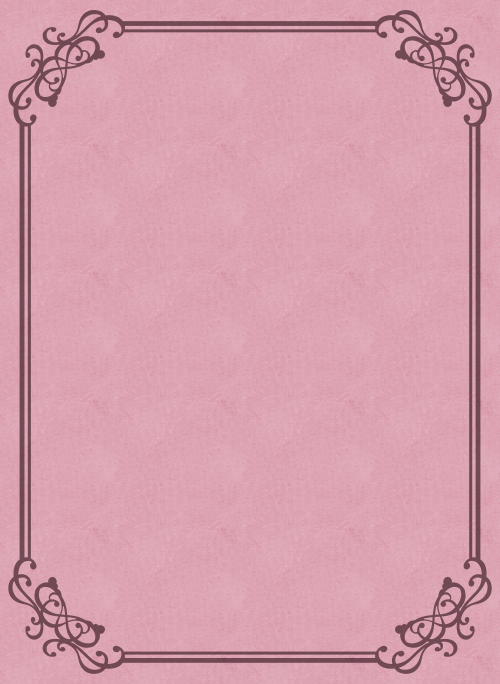「大丈夫? 由衣子ちゃん」
游さんの胸に飛び込むような形になったから、特に何の衝撃もない。
「……私は、大丈夫です。游さんは?」
「僕は、うん。大丈夫」
「ごめんなさい、今どきます」
私は游さんの顔の左右の床に両手をついて、起き上がろうとする。しかし、落ちていた生クリームでつるりと滑った。
「うわっ」
「どうしたの、由……んむ」
運悪く、私の唇は、真下にあった游さんの唇に着地した。やわらかくて温かくて、心地よい。……じゃなくて。
「ごめんなさいっ!」
私は慌てて游さんから離れた。
游さんはムクリと起き上がると、おそらく真っ赤であろう私の頬に触れる。
どきんと胸が高鳴った。
高鳴ってしまった。このままキスされるのではないかと思ってしまったから。
「由衣子ちゃん」
「……は、はい」
「クリームがついてるよ」
游さんの親指は私の右頬をなでて、そっと離れてていく。
「なんだ、クリーム」
「え?」
游さんが聞き返す。私は慌てて頭をふった。
「ううん、何でもないです。……すみません」
自意識過剰。それでいて、ネガティブ。
「……じゃあ、僕シャワー浴びてこようかな」
「あ、はい」
「由衣子ちゃんは先に寝てていいからね」
「……でも」
「いいから、寝てて」
求められたら全力で拒否するのに、そうじゃないと落ち込む。私って女は、本当に面倒な生き物だと思う。
「ほら、もう二時だからさ。僕には気を使わないでくれていいよ」
なんて言いながらにこりと笑う游さんは、なんて気遣いのできる男なんだろう。
「じゃあ、はい」
私は素直に彼の言うことに応じることにした。
「うん、いいこ」
不意に頭をなでられた私は、ふにゃっと顔が綻むのを堪える事が出来なかった。