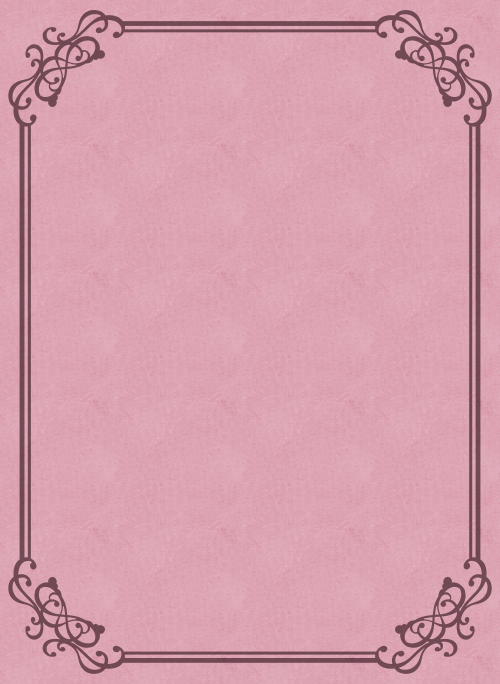「さっぱりした~、この化粧水借りてもいいかな」
シャワーを浴び終えると、私は鏡の前に置いてあるボトルに手を伸ばした。
男性誌などで見かける全身使用の化粧水と乳液は、元カレの隆も愛用していたものだ。
始め見た時は男のくせにと思ったが、冷暖房で乾燥すると聞いて、確かにそうかもと納得したのを思い出す。
「游さんも、意外とスキンケアとか気を使う人なのかな?」
勝手な想像を廻らしながら、化粧水を手のひらに少し出し顔全体にパッティングした。それからドライヤーで髪を乾かして、借りた部屋着に袖を通す。
「游さん、バスタオルって……」
どうしたらいいですか?そう聞きたかったのに、風呂場から出ると部屋には游さんの姿がなかった。
「あれ、どこに行ったんだろう?」
出掛けるなんて、ひと言もいっていなかった。もしかして、職場から呼び出しがあったんだろうか。
どちらにせよ、私はこのままこの部屋にいることしかできない。
「携帯くらい、聞いておけばよかった」
濡れたバスタオルは、畳んで浴槽のふちにかけて置く。おそらく洗濯機はベランダにあるのだろう。スリガラスの窓に四角い形が透けて見えた。
「……なんか飲みたい」
喉が渇いていた私は、そう独りごちる。
冷蔵庫の中に、何かあるだろうか。でも、勝手に漁るわけにはいかない。
小さなキッチンに目をやると、水切り籠に伏せられたコップが目に入った。蛇口を捻れば水が出る。しかし、東京の水道水はまずいのだ。
「コンビニに走ろうかな」
深夜だし、この格好のまま行ってしまおう。そう考えてお財布を手に取った時、玄関のドアが静かな音を立てて開いた。