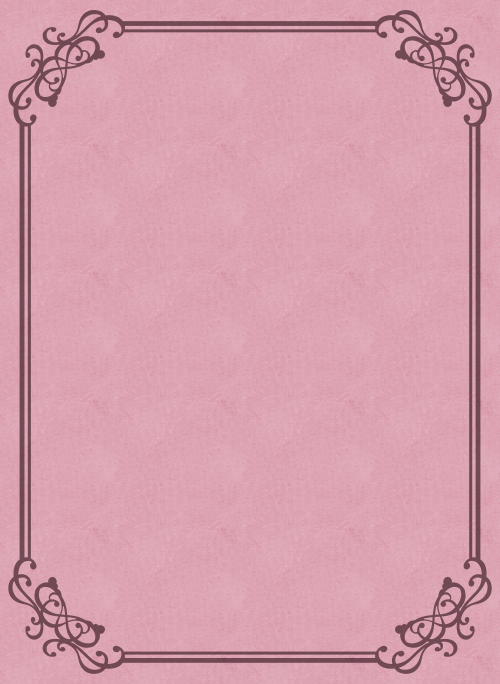翌朝目を開けると、すぐ近くに游さんの顔があった。
朝日に透けて茶色に染まった髪は、肌の白い游さんによく似合っていて、伏せられた目蓋には私よりも長い睫毛がある。少し開き気味の唇は無防備でかわいい。キスしたくなる程、游さんが愛おしい。
「あんまり見つめないでくれる?」
そう言って游さんは目を開けた。至近距離で見つめ返されて、私は息を詰める。
「……っ、やだ。お起きていたんなら早く言ってください!」
「うん。でも、そのままにしてたらキスくらいしてもらえるかなと思って。……図星?」
していたかもしれない。なんて言うもんか。
「まさか、そんなことしません!」
「どうしてしないの? 昨日、あんなに待たせておいてそれはないよ。……して」
游さんは自分の唇を指さして言う。
「じ、じゃあ、目、閉じてください!」
「うん、こう?」
言われて素直に目を閉じる游さんに胸キュンしてしまったのは秘密にしておこう。
私は游さんに近づいて、そっと唇を重ねる。
ああ、やっぱり愛おしい。涙が出そうになるほど幸せだ。心から好きだと思える人の傍にいられることは、はなんて素晴らしいんだろう。心の中で呟いて、そっと唇を離す。
すると游さんは「こんなんじゃ足りない」そういって、またキスをする。キスをしながら游さんは私のバスローブの紐をほどく。
「……朝から、するんですか?」
こんな明るい場所じゃ、恥ずかしさで私の顔が真っ赤に染まっているのも、幸せで泣きそうなのも、全部見られてしまう。
「だって、したいから」
今までのように遠慮しない游さんはとことん強引だ。うわべだけのダメやイヤは聞き入れてもらえない。
そうかと思えば、「いやならやめてもいいよ?」とワザと焦らす。
「……もう。游さんって意地悪ですね」
「いまさら気づいても遅いよ」
ニヒルに笑う彼も好きだ。自分ではどうしようもないくらいに大好きだ。