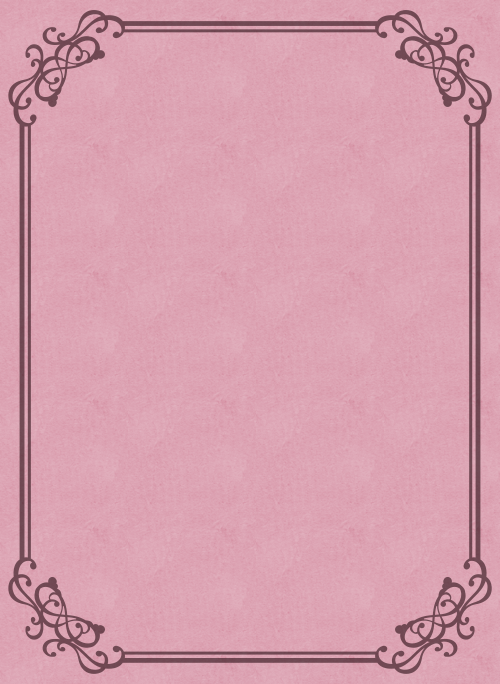「ねえ、由衣子ちゃん。ひとつだけ聞いていい?」
「……はい」
私は毛布から顔を出すと恐る恐る游さんをみつめた。
「由衣子ちゃんは僕が嫌いになったから家を出て行ったの?」
「違います」
「じゃあ、どうして?」
游さんの言葉に私はどうこたえるか悩んで、結局素直に思ったままを伝えることにした。
「……むしろ、好きだったから身を引いたんです。だって、游さんは游さんにふさわしい女性と結婚するんでしょう? それを傍で見ているなんて、私には出来ないと思ったから」
言い終わるころには、私の目からは大粒の涙がこぼれ落ちていた。游さんの顔が滲んでもう見えない。
「だから出て行ったの?」
「そうです」
「いけない子だね。そんな理由で出て行くなんて」
「ごめんなさい、游さん」
「……ねえ、由衣子ちゃん。もうどこにもいかないって約束して? そうすれば許してあげてもいいよ」
それってつまり、傍にいてもいいってこと?
「游さんはそれでいいんですか?」
「いいもなにも、僕は、あの靴の持ち主を探すためなら、世界中のどこへだって行くつもりだった。シンデレラに出てくる王子みたいに必死でね」
「本当ですか?」
「もちろん、本当だよ。それくらい君は僕に取ってにとって大切な存在になってしまったんだ」
そんなふうにいわれたら、余計に涙が止まらなくなる。私はまるで子供みたいに泣いた。