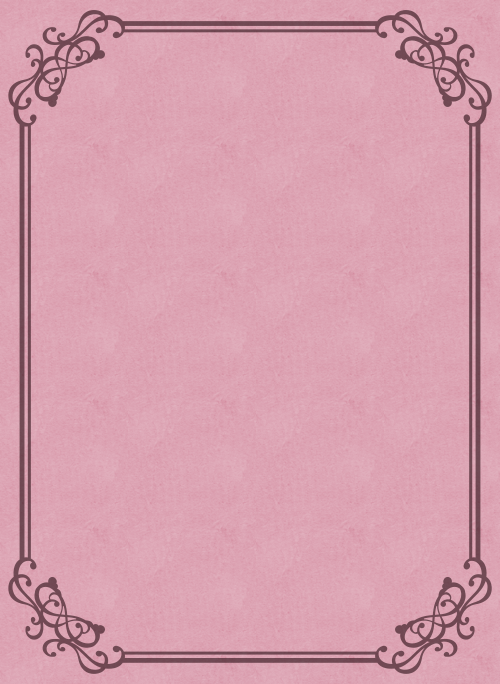私が意識を取り戻したのは、倒れてからどれくらい時間が経った後だっただろう。
右手に触れる懐かしい温もりを感じて、私はそれをしっかりと握った。
そしてゆっくりと目を開けると、私を心配そうに覗き込むひとりの男性がそこにいた。そのひとは、真っ白な服を身に纏っていて、まるで王子様みたいに見えた。
「由衣子ちゃん、目が覚めた?」
「……游さん?」
どうしてここに居るのか、聞きたかったけど言葉にはならなかった。
「廊下で倒れたんだよ。ここは処置室のベッド。軽い脱水と、貧血。それ以外に異常はなさそうだけど、少し見ない間に、だいぶ痩せたんじゃない?」
游さんはまるでいたわるような眼差しを向ける。
私には優しくしてもらう権利なんてないのに。
気まずさに耐え兼ねた私は、毛布を引き寄せて顔を隠した。
「どうしたの、由衣子ちゃん?」
「……ごめんなさい、游さん」
「なんで謝るの?」
「だって、黙って出て行ってりしたから。……怒ってますよね」
「もちろん、怒ってるに決まってるだろ!」
予想通りの言葉だった。自分のしたことを考えれば、責められてしかるべきことだと分かっているつもりだったのに、どこかで笑って許してくれる気がしていた。そんな甘えた考えに辟易しながらも、悲しくて涙が滲んだ。