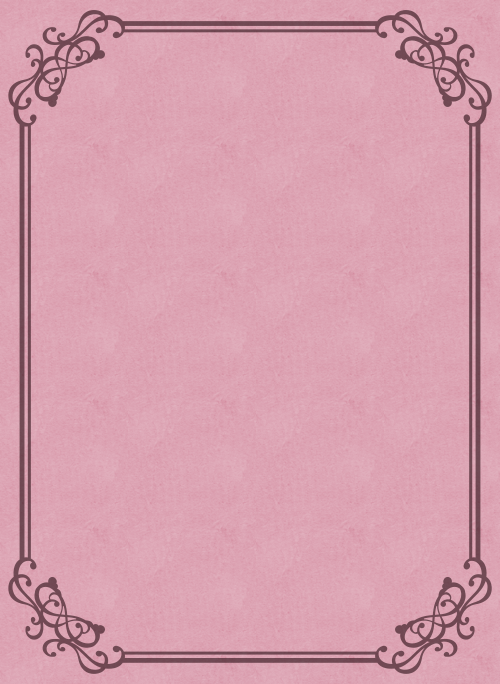「自分でもよくわかんない」
それが本音だ。
「なにが分かんないのよ、好きなんでしょ、游さんのこと。游さんだって、あんたのこと好きだから電話かけてくるんじゃない」
「游さんの気持ちは分からないけど、私は好きだよ。でも、身分が違い過ぎる」
大病院の跡取りの游さんと私とじゃ、釣り合わない。
「身分って、江戸時代じゃあるまいし。好きならそれでいいじゃない。それに玉の輿、乗りたかったんでしょ?」
玉の輿に乗りたいだなんて言えたのは、私が身の程を知らなかったからだ。でも今は、そうじゃない。
「……確かに私、よく言ってたね。でも、今はそういうのどうでもいいの。游さんならお金持ちじゃなくても好きだって思えたんだよね」
「じゃあ、なおさら会って話しなよ! 彼に頼んで呼んであげる」
紘子はすぐさまスマホを取り出して、電話を掛けようとする。
「慎一郎さんに? いい、いいよ。もういい」
私は慌てて紘子を止めた。すると紘子は大きなため息を吐く。
「……はぁ。なにがいいのよ、好きなんでしょ?」
「好きだけど、私は游さんにふさわしくないから」
「あそ。なら勝手にしな」
紘子はそう言って、レバーの塩焼きをひと串平らげる。そして、熱燗を継ぎ足して飲み干した。
「ごめん、紘子」
「謝るなら游さんに謝んなよ」
「そうだね」
もし会えたら、何も言わずにアパートを飛び出してごめんなさいって言う。そして、好きでしたって伝えたい。
でも、もうできない。いまさら、会いたいだなんて言えない。