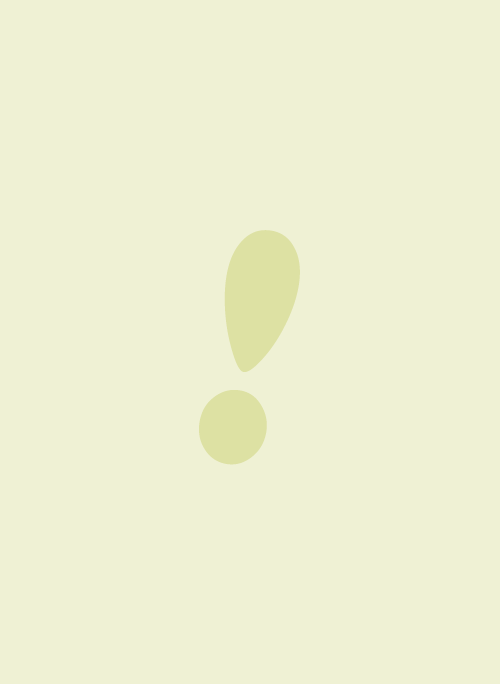「嫌だ!!!!!!嫌だ!!!!!!もう嫌だ!!!!!!」
誰かの悲痛な叫びが聞こえた。
この声には聞き覚えがある。
初めての夢で聞いた、元気がなかった女の人の声だ。
抑揚のないあのか細さはどこにいったのか、
ガシャン、パリーンと何かが壊れる音もする。
「おいおい、いい加減にしろよ。」
うんざりしているような、男の人の低い声が聞こえた。
それは女の人に呼び掛けている。
「一体何回部屋をめちゃくちゃにしたら気が済むんだよ。誰が片付けてると思ってんだ?」
「うるさい!!!!!!うるさいうるさい!!!!!!
こうなったのもあんたのせいよ!!!!!!あんたが、私をこんなにさせたんでしょ!!!!!!」
「俺は何もしてねぇよ。」
女の人の方が一方的に男の人につっかかっている。
男の人は冷静に答えるが、女の人は聞く耳も持たないようだった。
「あんたが、仕事クビになったから私は身を犠牲にして金を稼ごうとしたのに!!!!!!なのに契約が切られて、余計に金がかかって!!!!!!」
「知らねぇよ。俺は金を稼げって頼んでない。自業自得だろ。」
ガシャン、ガシャン‼
また破壊される音が聞こえる。
「あれだけ痛い思いしたのに!!!!!!どうして!?責任くらい取りなさいよ!!!!!!」
「お前が勝手にやったことなんだよ!」
ついに、男の人の怒鳴り声がした。
バシッという鈍い音がして、女の人の悲鳴が響く。
「もう限界だ。うんざりだ。
お前のことなんかもう好きじゃない。いつまでも餓鬼の癇癪に付き合っている暇ないんだよ。
別れてくれ。」
「そんな!!!ねぇ、待って、考え直して!!!!」
「嫌だね。お前の顔なんかもう見たくない。二度と俺に近寄るな。」
そして、ドアが強く閉まる音が聞こえた。
その後をすぐに追ったのは、悲痛な女性のむせび泣く声だった。
ドンドンドン、ドンドンドン。
現実の音によって、夢の世界から引き戻される。
ボンヤリとした意識で、ひどい夢だったと溜め息をついた。
聞くだけでも疲れる夢。
視界がなかったことがありがたい。
これは続きだったのだろうか。
とはいえ何だか苦しかった。訳の分からない感情がせり上がってくる。
どうして?
女の人の叫びがあまりにも悲痛だったから?
でも女の人は誰だか分からないでしょう?
自分とは何も関係ないはずでしょう?
他人の声を聞いて、どうしてこんな気持ちになるんだろう。
不思議で仕方がない。
朦朧とする意識の中、動くことはままならなかった。
机に身を縮こまったまま、祭壇の方を見る。
いつも通り、アドラーは祈っている。
でも様子が少し変だった。
「何故あなたはそうして僕達を殺そうとしているんだ。」
彼は女神像に話しかけていた。
小さな声だが、そこには憎悪が込められている。
「僕達はあなたに望まれなかった。
でもあなた以外選択をすることもできなかった。
だからこんな最悪な世界で、懸命に生きてきたんだ。
あなたが与えた毒の混じった食事を必死で飲み込んで。ナイフの雨から身を隠して。」
私は女神像の両端に赤い砂が散らばっているのを目にした。
それは全て、砂時計の天の皿から少しずつこぼれ落ちている。
一体何が起きたのだろう?
「なのにあなたはいとも容易く僕達を殺そうとしている。この世界で終わらせようとしている。あなたに不都合があるからか?僕達はあなたに会うことが出来ないのか?
生きる幸せを感じることは出来ないのか?」
パキッ
砂時計に一線、ヒビが加わった。
その音が癪に障ったのか、勢いよく彼は立ち上がる。
「お願いだ。たとえそうだとしても、せめてあなたはあの子を選んでくれ。
僕は選ばれなくていい。どうなってもいいから、どうかあの子を!」
アドラーが指す『あの子』は嫌でも分かる。
自分のことだ。
途端に体に力が入った。ふらふらと立ち上がって、彼に近づく。
「リラ……」
アドラーは振り返るなり、私の名前を呼ぶ。
「あと少しで、あと少しで、終わるからな……苦しくて、辛い日々が………」
パシッ
鋭い音が響いた。
私の手の平が、強く彼の頬を打ったからだ。気がついたら、打ってしまっていた。
でも沸き上がる感情は、怒りと悲しみばかりだった。
もう訳が分からない。
彼の言った言葉なんて、頭の中に入らない。
「どうしてよ?」
わなわなと、口元が震える。
「どうして、そんなことを言うの?」
目から大粒の涙が流れる。
「私だけ、残っても何も出来ないのに。」
足元から、崩れ落ちた。
「あなたがいない世界なんて、何の意味もないのに。」
「リラ、違うんだ。」
頬を打たれても、彼は動じなかった。
涙で濡れた私の頬を撫でる。
「彼女がそばにいる。
君を愛してくれるんだ。」
「嫌だ!アドラーがいないと嫌だ!!!!!!
二人でいたいの。二人で、生きていきたいの。
どうして殺されようとしてるの?あなたを殺した人なんかと、私は長生きなんてしたくない!!!」
「それでも彼女は僕達の……」
何を言おうとしたのか、アドラーは口をつぐんだ。
間をおいて、目をきゅっと閉じる。
「選択を委ねられたのは彼女だ。
彼女が僕達をこれからどうするのかを決める。それまで僕達は何もすることは出来ない。」
「本当に?」
「あぁ、僕達に選択肢は与えられてない。」
沈黙が、流れた。
何もすることが出来ない。
たとえ、彼の言葉通り自分たちの命がかかっていたとしても。
女神様、お願いです。
二人揃う選択をしてください。一人欠けたとしたら、生きることは出来ません。きっと壊れてしまうでしょう。
両手の袖を破った。
気にしない、どうせ明日には元通りになるんだから。
ただの布になった二つの袖を砂時計の天の皿に巻き付けた。
これで中の砂がこぼれることはない。
少なくともこうやって傷を塞げば、ずっと彼といられるような気がしたのだ。
とりあえず、安心したかった。
誰かの悲痛な叫びが聞こえた。
この声には聞き覚えがある。
初めての夢で聞いた、元気がなかった女の人の声だ。
抑揚のないあのか細さはどこにいったのか、
ガシャン、パリーンと何かが壊れる音もする。
「おいおい、いい加減にしろよ。」
うんざりしているような、男の人の低い声が聞こえた。
それは女の人に呼び掛けている。
「一体何回部屋をめちゃくちゃにしたら気が済むんだよ。誰が片付けてると思ってんだ?」
「うるさい!!!!!!うるさいうるさい!!!!!!
こうなったのもあんたのせいよ!!!!!!あんたが、私をこんなにさせたんでしょ!!!!!!」
「俺は何もしてねぇよ。」
女の人の方が一方的に男の人につっかかっている。
男の人は冷静に答えるが、女の人は聞く耳も持たないようだった。
「あんたが、仕事クビになったから私は身を犠牲にして金を稼ごうとしたのに!!!!!!なのに契約が切られて、余計に金がかかって!!!!!!」
「知らねぇよ。俺は金を稼げって頼んでない。自業自得だろ。」
ガシャン、ガシャン‼
また破壊される音が聞こえる。
「あれだけ痛い思いしたのに!!!!!!どうして!?責任くらい取りなさいよ!!!!!!」
「お前が勝手にやったことなんだよ!」
ついに、男の人の怒鳴り声がした。
バシッという鈍い音がして、女の人の悲鳴が響く。
「もう限界だ。うんざりだ。
お前のことなんかもう好きじゃない。いつまでも餓鬼の癇癪に付き合っている暇ないんだよ。
別れてくれ。」
「そんな!!!ねぇ、待って、考え直して!!!!」
「嫌だね。お前の顔なんかもう見たくない。二度と俺に近寄るな。」
そして、ドアが強く閉まる音が聞こえた。
その後をすぐに追ったのは、悲痛な女性のむせび泣く声だった。
ドンドンドン、ドンドンドン。
現実の音によって、夢の世界から引き戻される。
ボンヤリとした意識で、ひどい夢だったと溜め息をついた。
聞くだけでも疲れる夢。
視界がなかったことがありがたい。
これは続きだったのだろうか。
とはいえ何だか苦しかった。訳の分からない感情がせり上がってくる。
どうして?
女の人の叫びがあまりにも悲痛だったから?
でも女の人は誰だか分からないでしょう?
自分とは何も関係ないはずでしょう?
他人の声を聞いて、どうしてこんな気持ちになるんだろう。
不思議で仕方がない。
朦朧とする意識の中、動くことはままならなかった。
机に身を縮こまったまま、祭壇の方を見る。
いつも通り、アドラーは祈っている。
でも様子が少し変だった。
「何故あなたはそうして僕達を殺そうとしているんだ。」
彼は女神像に話しかけていた。
小さな声だが、そこには憎悪が込められている。
「僕達はあなたに望まれなかった。
でもあなた以外選択をすることもできなかった。
だからこんな最悪な世界で、懸命に生きてきたんだ。
あなたが与えた毒の混じった食事を必死で飲み込んで。ナイフの雨から身を隠して。」
私は女神像の両端に赤い砂が散らばっているのを目にした。
それは全て、砂時計の天の皿から少しずつこぼれ落ちている。
一体何が起きたのだろう?
「なのにあなたはいとも容易く僕達を殺そうとしている。この世界で終わらせようとしている。あなたに不都合があるからか?僕達はあなたに会うことが出来ないのか?
生きる幸せを感じることは出来ないのか?」
パキッ
砂時計に一線、ヒビが加わった。
その音が癪に障ったのか、勢いよく彼は立ち上がる。
「お願いだ。たとえそうだとしても、せめてあなたはあの子を選んでくれ。
僕は選ばれなくていい。どうなってもいいから、どうかあの子を!」
アドラーが指す『あの子』は嫌でも分かる。
自分のことだ。
途端に体に力が入った。ふらふらと立ち上がって、彼に近づく。
「リラ……」
アドラーは振り返るなり、私の名前を呼ぶ。
「あと少しで、あと少しで、終わるからな……苦しくて、辛い日々が………」
パシッ
鋭い音が響いた。
私の手の平が、強く彼の頬を打ったからだ。気がついたら、打ってしまっていた。
でも沸き上がる感情は、怒りと悲しみばかりだった。
もう訳が分からない。
彼の言った言葉なんて、頭の中に入らない。
「どうしてよ?」
わなわなと、口元が震える。
「どうして、そんなことを言うの?」
目から大粒の涙が流れる。
「私だけ、残っても何も出来ないのに。」
足元から、崩れ落ちた。
「あなたがいない世界なんて、何の意味もないのに。」
「リラ、違うんだ。」
頬を打たれても、彼は動じなかった。
涙で濡れた私の頬を撫でる。
「彼女がそばにいる。
君を愛してくれるんだ。」
「嫌だ!アドラーがいないと嫌だ!!!!!!
二人でいたいの。二人で、生きていきたいの。
どうして殺されようとしてるの?あなたを殺した人なんかと、私は長生きなんてしたくない!!!」
「それでも彼女は僕達の……」
何を言おうとしたのか、アドラーは口をつぐんだ。
間をおいて、目をきゅっと閉じる。
「選択を委ねられたのは彼女だ。
彼女が僕達をこれからどうするのかを決める。それまで僕達は何もすることは出来ない。」
「本当に?」
「あぁ、僕達に選択肢は与えられてない。」
沈黙が、流れた。
何もすることが出来ない。
たとえ、彼の言葉通り自分たちの命がかかっていたとしても。
女神様、お願いです。
二人揃う選択をしてください。一人欠けたとしたら、生きることは出来ません。きっと壊れてしまうでしょう。
両手の袖を破った。
気にしない、どうせ明日には元通りになるんだから。
ただの布になった二つの袖を砂時計の天の皿に巻き付けた。
これで中の砂がこぼれることはない。
少なくともこうやって傷を塞げば、ずっと彼といられるような気がしたのだ。
とりあえず、安心したかった。