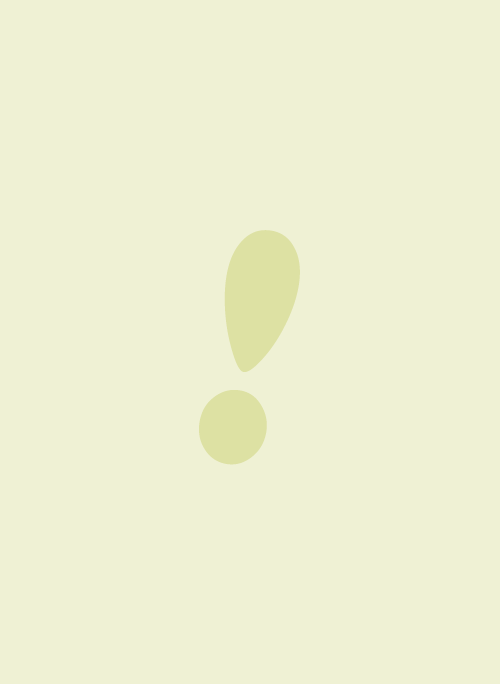「いい加減になさってください。」
ここに来てから約半年。
初めて夢の中で声が聞こえた。
はっとして、夢だというのに緊張が走る。
低く冷たい、女の人の声だった。
誰かに向かって怒っているかのように、言葉にとげが感じられる。
「あなた一人の身じゃないんですよ。影響が出て流れてしまったらどうするんですか。」
すると、別の女の人の声が聞こえた。
か細くて思い詰めたような、重苦しい声だ。
「私だって好きでこんなことになったんじゃないわよ。流れるものなら流れてほしいわ。
もう契約が破棄されたんだから。」
「だからって、諦めるのですか?せっかく二人があなたを選んでくれたというのに。」
低く冷たい声の女性が、叫ぶように言う。
だが、か細い声の女性は変わらず抑揚もなく答える。
「どうなってもいいのよ、もう。」
はっと目を覚ました。
頭が痛い。ぐらぐらする。
視線のすぐ先で、アドラーが心配そうにこちらを覗きこんでいる。
目覚めた場所は珍しく、外の箱庭だった。
箱庭には暇潰しに出る以外行く機会はない。寝床に使うなどもってのほかだ。
うめき、体を起こそうとした。
でも起きたばかりで動くことができない。
「大丈夫か?リラ。」
アドラーが上体を起こすのを手伝ってくれた。
ありがとう、と礼を言って微笑んだ。
その声には疲労が混じっている。
「私、どうしてこんなところに寝てたの?」
彼に尋ねると、寝てたんじゃないと訂正された。
「倒れていたんだ。」
少し、彼は険しい顔つきだった。
こちらの額に手をあてて、ふっと息を吐く。
「顔色が悪いが、熱はないみたいだな。」
そして、立てるか、と尋ねた。
うなずいて、フラフラしながらも立ち上がる。
まだ頭に痛みが走るが、我慢できる範囲なので黙っていた。
「ねぇ、アドラー。」
かすれた声で呼び掛ける。
彼はうん、と首をかしげ、話を促してくれる。
「あなたは聞いたこと、ある?
他の女の人の声。」
とにかく、怖かった。
初めて他人の声。この二人しかいない世界に混じってきた、誰かの気配。不安。
それがとにかく怖かったのだ。
「リラ、お前……」
「夢の中は何も見えなくて聞こえないはずなのにね、今日は初めて他の人の声が聞こえたの。」
少し震えながら、両手の袖をぎゅっと握りしめる。
「誰なのかわからないわ。私はあなたと私しか知らないもの。
知らないからこそ、怖くてならないの。」
アドラーは黙っていた。
そのまま話を続けるように、真剣な眼差しをこちらに向けている。
「二人の女性の声がしたわ。
二人とも、なんだか喧嘩しているみたいだった。
あの人たちは誰なの?どうして喧嘩していたの?」
彼は首を振る。
「僕にも分からない。」
「声を聞いたことは?」
「何度かある。だが、何を言っているのかは聞き取ることはできなかった。」
答えた後、彼は私から少し視線をずらした。
「彼女たちはなんと言っていたんだ?」
不安な気持ちに煽られながら、私は夢の内容を思い出した。
一番印象的だった言葉を口にする。
「流れるものなら流れてほしい…」
カッとアドラーは目を見開いた。
「せっかくあなたを二人が選んでくれたというのに。」
「どうなってもいいのよ、もう。」
言葉を言い終える前に、彼は私を抱き寄せた。
きつく抱き締めるその両手は、私と同じように震えている。
「嫌だ。」
アドラーが呟いた。
「嫌だ、嫌だ。失いたくない。僕もお前も終わりたくない。」
「アドラー……?」
「終わりじゃない。終わってはならないんだ。ここで……」
きつく抱き締める手は、いっそう力を強めた。
「守ってみせる。」
ただ事ではないような気がした。
あのアドラーが怯えている。
抱き返す余裕もなく、私はぼうっとしたまま停止していた。
「大丈夫だ。僕がお前を守る。」
ここに来てから約半年。
初めて夢の中で声が聞こえた。
はっとして、夢だというのに緊張が走る。
低く冷たい、女の人の声だった。
誰かに向かって怒っているかのように、言葉にとげが感じられる。
「あなた一人の身じゃないんですよ。影響が出て流れてしまったらどうするんですか。」
すると、別の女の人の声が聞こえた。
か細くて思い詰めたような、重苦しい声だ。
「私だって好きでこんなことになったんじゃないわよ。流れるものなら流れてほしいわ。
もう契約が破棄されたんだから。」
「だからって、諦めるのですか?せっかく二人があなたを選んでくれたというのに。」
低く冷たい声の女性が、叫ぶように言う。
だが、か細い声の女性は変わらず抑揚もなく答える。
「どうなってもいいのよ、もう。」
はっと目を覚ました。
頭が痛い。ぐらぐらする。
視線のすぐ先で、アドラーが心配そうにこちらを覗きこんでいる。
目覚めた場所は珍しく、外の箱庭だった。
箱庭には暇潰しに出る以外行く機会はない。寝床に使うなどもってのほかだ。
うめき、体を起こそうとした。
でも起きたばかりで動くことができない。
「大丈夫か?リラ。」
アドラーが上体を起こすのを手伝ってくれた。
ありがとう、と礼を言って微笑んだ。
その声には疲労が混じっている。
「私、どうしてこんなところに寝てたの?」
彼に尋ねると、寝てたんじゃないと訂正された。
「倒れていたんだ。」
少し、彼は険しい顔つきだった。
こちらの額に手をあてて、ふっと息を吐く。
「顔色が悪いが、熱はないみたいだな。」
そして、立てるか、と尋ねた。
うなずいて、フラフラしながらも立ち上がる。
まだ頭に痛みが走るが、我慢できる範囲なので黙っていた。
「ねぇ、アドラー。」
かすれた声で呼び掛ける。
彼はうん、と首をかしげ、話を促してくれる。
「あなたは聞いたこと、ある?
他の女の人の声。」
とにかく、怖かった。
初めて他人の声。この二人しかいない世界に混じってきた、誰かの気配。不安。
それがとにかく怖かったのだ。
「リラ、お前……」
「夢の中は何も見えなくて聞こえないはずなのにね、今日は初めて他の人の声が聞こえたの。」
少し震えながら、両手の袖をぎゅっと握りしめる。
「誰なのかわからないわ。私はあなたと私しか知らないもの。
知らないからこそ、怖くてならないの。」
アドラーは黙っていた。
そのまま話を続けるように、真剣な眼差しをこちらに向けている。
「二人の女性の声がしたわ。
二人とも、なんだか喧嘩しているみたいだった。
あの人たちは誰なの?どうして喧嘩していたの?」
彼は首を振る。
「僕にも分からない。」
「声を聞いたことは?」
「何度かある。だが、何を言っているのかは聞き取ることはできなかった。」
答えた後、彼は私から少し視線をずらした。
「彼女たちはなんと言っていたんだ?」
不安な気持ちに煽られながら、私は夢の内容を思い出した。
一番印象的だった言葉を口にする。
「流れるものなら流れてほしい…」
カッとアドラーは目を見開いた。
「せっかくあなたを二人が選んでくれたというのに。」
「どうなってもいいのよ、もう。」
言葉を言い終える前に、彼は私を抱き寄せた。
きつく抱き締めるその両手は、私と同じように震えている。
「嫌だ。」
アドラーが呟いた。
「嫌だ、嫌だ。失いたくない。僕もお前も終わりたくない。」
「アドラー……?」
「終わりじゃない。終わってはならないんだ。ここで……」
きつく抱き締める手は、いっそう力を強めた。
「守ってみせる。」
ただ事ではないような気がした。
あのアドラーが怯えている。
抱き返す余裕もなく、私はぼうっとしたまま停止していた。
「大丈夫だ。僕がお前を守る。」