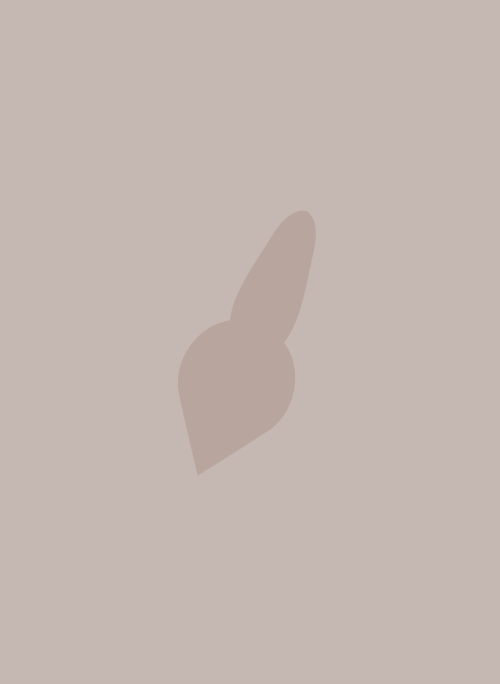しどろもどろする僕を見てたまり兼ねたのか、彼女は僕の手を取った。
「私は本気で決意しているの。いいわ。一緒に行きましょう。私も貴方と共犯になる。」
「ダメだ!」
僕は思わず手を振り払った。そんな事をさせる訳にはいかない。
「頼む。帰ってくれ。僕の事は忘れて、ちゃんと幸せになってくれ。」
しかし、彼女は微動だにしなかった。
「私は一度決めた事は曲げないわ。きっと大丈夫よ。さあ。」
「でも…」
僕の煮え切らない態度に、彼女はついに痺れを切らした。
「じゃあ、もう私から行くわよ。」
そう言うと、彼女は思い切り門を開け、中に入っていった。
僕は彼女を追い掛けた。
彼女の、あまりに強い意志に、僕は折れた。彼女となら本当に何とかなるかもしれない、とさえ思っていた。
ドアノブに、二人で手をかけた。
ガギ…ギ…と錆びた蝶番が呻いて、ドアが開いた。と、同時に、得も言われぬ異臭と奇妙な光景が二人を襲った。
玄関にぶら下がる、黒い袋。
袋の表面が、どこかうごめいているように見える。
僕は玄関前の傘置きから傘を一本取ると、袋を突いた。
物凄い羽音と共に、黒い塊が飛び去った。
後に残されたのは、無数の小さな穴が開いた、女の首吊り死体であった。
「私は本気で決意しているの。いいわ。一緒に行きましょう。私も貴方と共犯になる。」
「ダメだ!」
僕は思わず手を振り払った。そんな事をさせる訳にはいかない。
「頼む。帰ってくれ。僕の事は忘れて、ちゃんと幸せになってくれ。」
しかし、彼女は微動だにしなかった。
「私は一度決めた事は曲げないわ。きっと大丈夫よ。さあ。」
「でも…」
僕の煮え切らない態度に、彼女はついに痺れを切らした。
「じゃあ、もう私から行くわよ。」
そう言うと、彼女は思い切り門を開け、中に入っていった。
僕は彼女を追い掛けた。
彼女の、あまりに強い意志に、僕は折れた。彼女となら本当に何とかなるかもしれない、とさえ思っていた。
ドアノブに、二人で手をかけた。
ガギ…ギ…と錆びた蝶番が呻いて、ドアが開いた。と、同時に、得も言われぬ異臭と奇妙な光景が二人を襲った。
玄関にぶら下がる、黒い袋。
袋の表面が、どこかうごめいているように見える。
僕は玄関前の傘置きから傘を一本取ると、袋を突いた。
物凄い羽音と共に、黒い塊が飛び去った。
後に残されたのは、無数の小さな穴が開いた、女の首吊り死体であった。