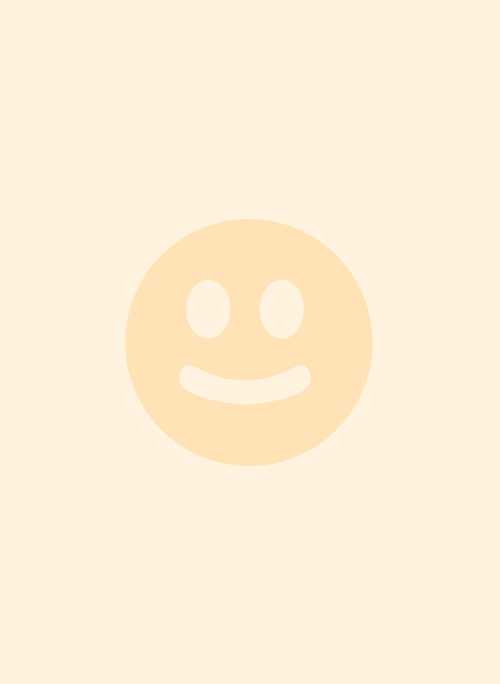ホルモンの焼ける匂いなど、まるで嗅いでいないように。
亮二と松岡は、鬼首の健啖な様をひたすらに睨んでいた。
こんな複雑な心境で、食欲など湧くものか。
「お前らが気に入らねぇってのも、わからんでもない。極道に飼われる為に、血反吐吐きながら殺しの技を身に付けた訳じゃねぇだろうからな」
箸休めにキムチを口に入れ、音を立てて咀嚼。
鬼首は箸を置いた。
「別に、お前らにヤクザをやれとは言わねぇ。今まで通りだ。仕事がねぇ時は好きにしててくれりゃいい。依頼はこれまで通りメールで指令を出す。そん時だけ、お前らは標的を消せばいい。要するにお前らは、鬼首會お抱えの殺し屋…鬼首會の客分だ」
代紋を背負うだの、背中に刺青を彫るだの、責任取る時は小指(エンコ)詰めるだの、そんな事は一切考えなくていい。
鬼首はそう言っているのだ。
亮二と松岡は、鬼首の健啖な様をひたすらに睨んでいた。
こんな複雑な心境で、食欲など湧くものか。
「お前らが気に入らねぇってのも、わからんでもない。極道に飼われる為に、血反吐吐きながら殺しの技を身に付けた訳じゃねぇだろうからな」
箸休めにキムチを口に入れ、音を立てて咀嚼。
鬼首は箸を置いた。
「別に、お前らにヤクザをやれとは言わねぇ。今まで通りだ。仕事がねぇ時は好きにしててくれりゃいい。依頼はこれまで通りメールで指令を出す。そん時だけ、お前らは標的を消せばいい。要するにお前らは、鬼首會お抱えの殺し屋…鬼首會の客分だ」
代紋を背負うだの、背中に刺青を彫るだの、責任取る時は小指(エンコ)詰めるだの、そんな事は一切考えなくていい。
鬼首はそう言っているのだ。