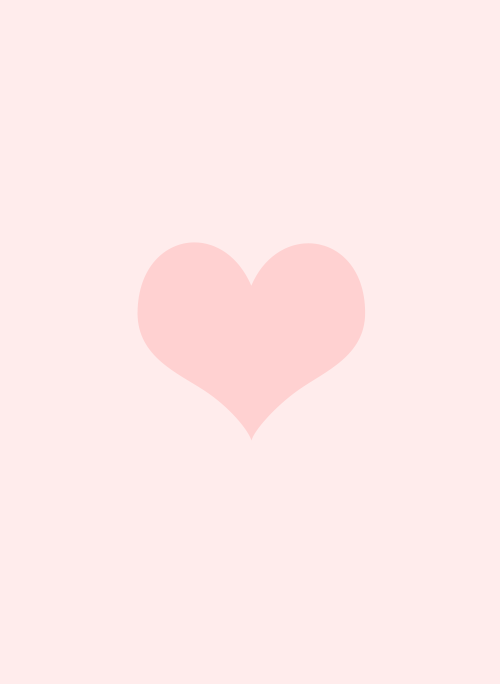「あ、え、あの、怪しい者ではありません!」
「いえ、怪しいとは思っていませんよ」
「や、そ、そうでした。あの、俺、紀ノ川亮介(きのかわ りょうすけ)です。ここの二一二号室に住んでます」
「同じマンションだったんですね。私は井波海音、三一五号室です」
頭を下げた私に、紀ノ川と名乗った彼は、おずおずと尋ねる。
「あの……俺、余計なことをしちゃいましたか?」
助けたことを聞いているのだろう。男女の痴話げんかと思われたのかもしれない。
私は急いで頷いた。
「本当に助かりました。ありがとうございます」
「でも……あれは彼氏さんですか?」
「違います! 全然、違います!」
あんな人、彼氏だなんて考えるだけで吐き気がしそうだ。
「昔の……知り合いです。こんなところで再会して……会いたくもないのに」
言いながら、私は我知らず涙を落としていた。最初、自分でも泣いていることに気がつかなかったから、雨が降ってきたのかと思い顔を上げた。
「あ、わっ! あの! わわわ、どうしよう。あ、これ、飲みますか!?」
向きあっている紀ノ川さんは、ひどく狼狽して手にぶら下げているコンビニのビニール袋から温かいミルクティーを取り出し渡してくれる。
「いえ、大丈夫です」
ズズッとみっともなく鼻をすする私に、紀ノ川さんは無理やりミルクティーのペットボトルを押しつけて、顔を背けた。