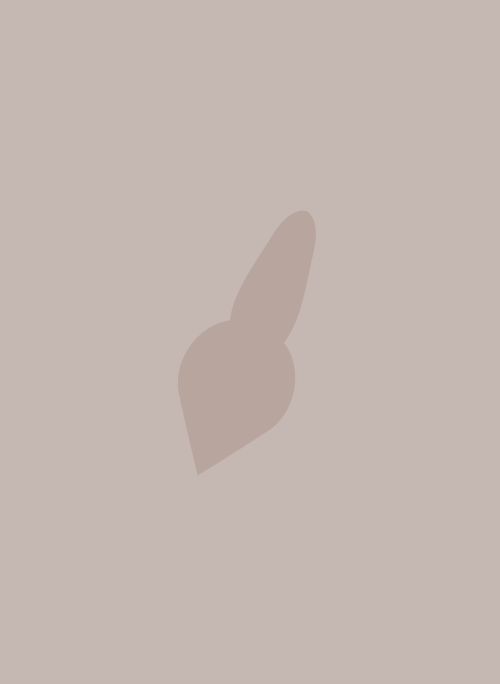次に私が目を覚ました時には、すでに日付が変わっていた。
右ポケットに入っていたケータイを取り出して、日時を確認するまでは、日付が変わっていたことなんて気付かなかった。
どうやら、丸一日近く寝ていたみたいだ。
右手をついて、ゆっくりと体を起こし、辺りを見渡す。
見慣れた四角い目覚まし時計に、横には私の愛読書と、私と彼が写っている写真が飾ってある。
ここは紛れも無く、私の寝室だった。
「あれからずっと眠ってたんだ……」
誰もいない寝室で、一人呟いた。
声にならない「う〜ん」という声を出しながら、体を伸ばして、眠気を覚ます。
その瞬間、私ははっとした。
車の中で眠っていたはずなのに、寝室で寝ていたことに今更気付いたのだ。
まさか、恭平が私をここまで運んでくれたのかな?
そして、その恭平の姿はこの部屋にはなかった。
私は起きたばかりで、思うように動かない体を起こし、リビングへと向かう。
部屋の電気はついていなかった。
それどころか、恭平の姿すら見当たらない。
机の上には冷めたおかゆが皿に盛ってあり、その脇には小さなメモ用紙が添えてあった。
右ポケットに入っていたケータイを取り出して、日時を確認するまでは、日付が変わっていたことなんて気付かなかった。
どうやら、丸一日近く寝ていたみたいだ。
右手をついて、ゆっくりと体を起こし、辺りを見渡す。
見慣れた四角い目覚まし時計に、横には私の愛読書と、私と彼が写っている写真が飾ってある。
ここは紛れも無く、私の寝室だった。
「あれからずっと眠ってたんだ……」
誰もいない寝室で、一人呟いた。
声にならない「う〜ん」という声を出しながら、体を伸ばして、眠気を覚ます。
その瞬間、私ははっとした。
車の中で眠っていたはずなのに、寝室で寝ていたことに今更気付いたのだ。
まさか、恭平が私をここまで運んでくれたのかな?
そして、その恭平の姿はこの部屋にはなかった。
私は起きたばかりで、思うように動かない体を起こし、リビングへと向かう。
部屋の電気はついていなかった。
それどころか、恭平の姿すら見当たらない。
机の上には冷めたおかゆが皿に盛ってあり、その脇には小さなメモ用紙が添えてあった。