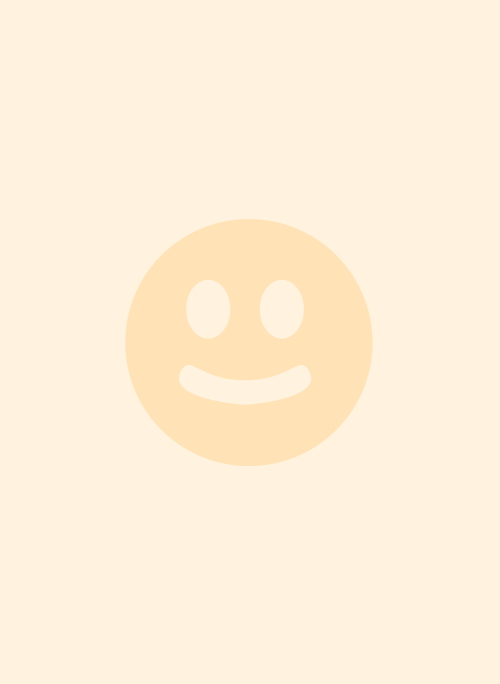ずかずかと踏み込んで、薄笑いで滅茶苦茶にするような人間だったのだろうか。もっと大人しいと思っていた。実際作業場でだって、ヤツはほとんど主張しない。あれは高校生の時の姿と被るのに―――――――――
好きのマジックで、私は幻想を夢みていたのかもしれない。初めて自分の気持ちを疑った。高校生の時の自分が信じられないって気持ちに動揺する。
その怒りはなんと、翌日まで持ち越して、私の体力をドンドン奪っていく。
本来なら幸せぬくぬく計画のはずだった夜は、いつもより増えたビール缶とボロボロになったクッションが二つの凄惨な夜になり、眠れもしなかった。悶々とうなされたのだ。
あんなに近くに平野の顔があった。
あんなにマジマジとヤツの顔を見たのは、初めてのことだ。
あんな間近で、あの目が私を見ていた。
夜の間中私は苦しんで、部屋のクッション並にボロボロの状態で出勤したから、翌日最初に顔をあわせた高峰リーダーに仰天される羽目になった。
「うわあっ!!・・・って・・・藤?何だその顔」
作業場の電気をつけずに黙って事務所へ入った私に気がついて、リーダーはそう叫ぶ。
私はちらっと上司の顔を見て、やる気のない会釈をした。
「おはよーございます・・・。昨日は明細、ありがとうございました」
「お、おお・・・。ちゃんと受け取ったんだろ?」
黙って頷いた。
高峰リーダーはまだドキドキしているらしい胸のあたりを押さえてたけれど、ようやく姿勢を戻してコホンと咳払いをする。