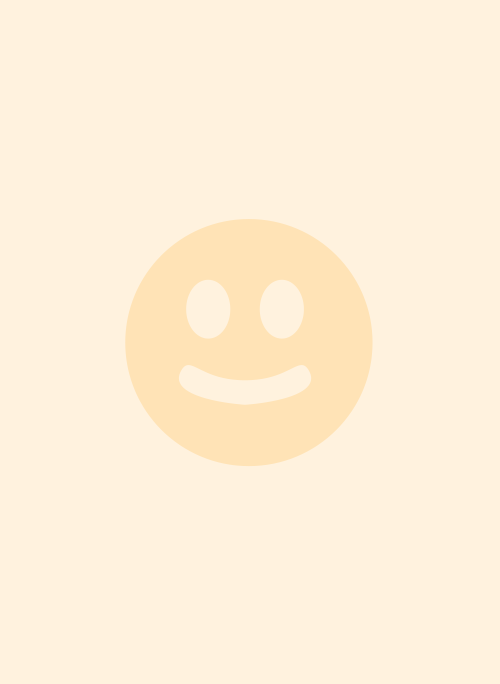「そんなこと藤は知らないんだから、仕方ないだろ。だけど、これが理由なんだ。大学に3年遅れで入ったのも、藤に酷い断り方をしたのも。・・・俺のことは忘れて欲しかったから」
・・・うわあ~。
私はもう泣きかけで、慌ててタオルを鞄から出す。目も鼻も心も痛い。
「いつアメリカから帰ってくるか判らなかったし、母親が闘病中で余裕もなくて。藤のことは、好き、だったから・・・告白は嬉しかったけど、応えられなくて」
そりゃそうだよね、そりゃそうだよね!私はタオルに顔を埋めながら何度も頷く。
あの時の平野を思ったら辛くて仕方ない。
「吉田に気持ちを話してたことは覚えてる。だから飲み会で、何かしら言われるだろうな、って。やっぱりそうなって、藤を泣かせてしまったな。・・・出来たら、余計なことだし知られたくなかったんだ。俺が好きだったことは」
平野はふう、と息をはくと、凝りを解すように肩を触り目を閉じて首をまわす。
「藤からの電話を貰って、あの夜は俺、兄貴に会いに行ったんだ。どうしたらいいかわからなくて、相談しに」
「お兄さん?結婚してるって言った?」
「そう。子供もいるんだ、2歳の姪が。俺が正月に顔を見せなかったことを叱られて、藤のことを聞いてくれて」
「うん」
「呆れられた。早く話してしまえ、って。またその子を傷付けて失いたいのか?って。でも重い話だろ?気軽には話せなくて・・・ごめん」
私は手を伸ばして平野の肩をさする。泣いているのかと思った。だけど平野はこっちを見て微笑し、シートベルトをしめてキーをまわす。