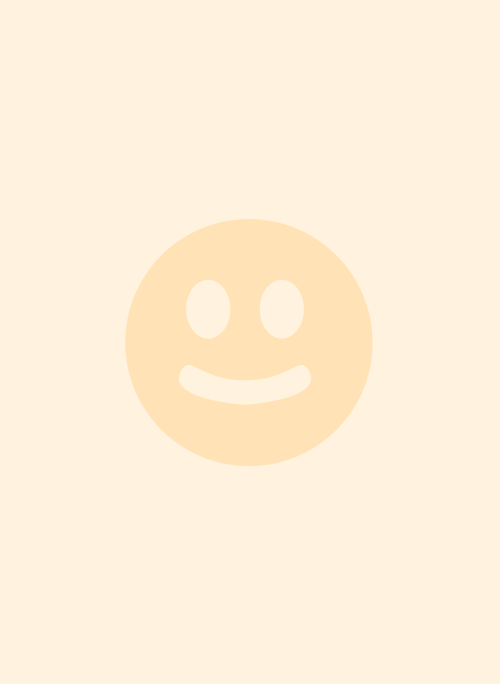「だけど今は別に好きじゃないのよ!避けてるのに近づいてくるから困ってるの」
「でもさ、元々タイプの男だったから好きだったんじゃないの~?なら今回だって好きになれると思うけど」
仁美がそう言ってサイドカーを飲み干す。一体いつまでバータイムは続くのだ。お腹が空いたぞ。私は恨めしくそう思って、二人の腕を平等につつく。
「酔っ払う前にご飯に行こうよ。お腹空いて倒れそうなんだけど」
「仕方ないな、移動しましょうか。ここにはいい男はいないみたいだし」
梓がそう言って、優雅にスツールから滑り降りる。私は仰天したが、どうやら彼女たちはここで奢ってくれる男が現れるのを待っていたようだった。
会計をして外へと出ると、私はブツブツと文句を言う。
「あんた達彼氏がいるんじゃなかったの!?」
何だ奢ってくれる男って!そう思って噛み付くと、ネオンに髪をキラキラと反射させながら、仁美がおほほと笑う(本当におほほって言った!)。
「バーで一緒に寝るわけじゃあるまいし、素敵な女の子たちがいたら奢りますっていう男がいて、それを受けるのは悪いことじゃないでしょ~」
「そう、にっこり笑ってありがとうって言えばいいの」
梓も同意する。私は目が点だ。何この人達・・・本当に同じ年?そして本当に私は彼女達の友達?いつのまに価値観が・・・。
「いやいや、あんた達ちょっとおかしいよ?」
「おかしいのは千明よ!青春を楽しみなさいよ、いつまでもチヤホヤはされないんだから」
こっちよ、と先導する仁美についていきながら、私は情けなく自分の姿を見下ろした。