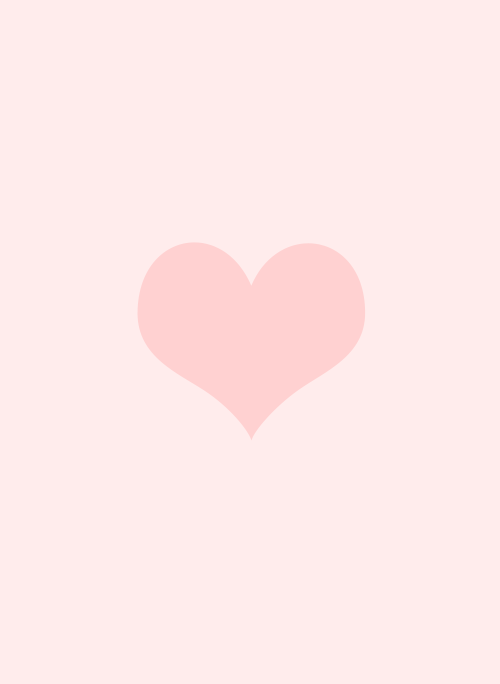清宮の言葉に苛ついた私は、私らしくもない強気の言葉を吐き出す。
「死ぬ気なんてないわよ!」
清宮は、依然として冷静だった。
その口から、冷酷ともいえる言葉が流れ出す。
「お前の右の掌。何で傷つけた?」
私は、咄嗟に右手を背中に隠す。
「答えろ、神崎…」
「あんたには、関係ないでしょ。」
喉の奥から絞り出した私の返事は、弱々しいものだった。
「死ぬ気なんてないわよ!」
清宮は、依然として冷静だった。
その口から、冷酷ともいえる言葉が流れ出す。
「お前の右の掌。何で傷つけた?」
私は、咄嗟に右手を背中に隠す。
「答えろ、神崎…」
「あんたには、関係ないでしょ。」
喉の奥から絞り出した私の返事は、弱々しいものだった。