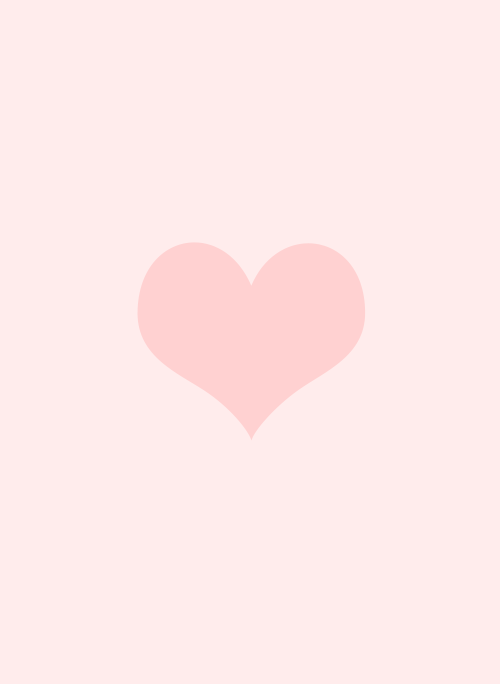十月――。
文化祭の喧騒もすでに思い出の中に収まった頃。
私は校内を駆け回っていた。
逃げ回っていた、のかもしれない。
(どこか――どこでもいいから、一人になれるところに行かなくちゃ)
私は、もう――いっぱいいっぱいだった。
クラスメートたちに良い顔をし続けるのが、愛嬌を振りまいて、わざとドジを踏んでみせて――。
でも、うんざりだった。
そんな道化――ピエロ――を演じ続けなくてはいけない現実に。
道化師である私を自分自身でも受け入れなくてはならなかった事実と、それを生み出したクラスの風潮に。
「はあっ……はあっ」
通称文化棟の最上階まで登りきると、息を整えた。
そしてさらに登ろうと折り返しの階段に目を向ける。
そこには黄色いロープが無意味にも引かれていた。
私はそれをものともせずにくぐり、さらに階段を上がっていく。
(やっと、落ち着ける。天国への階段って、もしかしたらこれかも)
そんなことを考えながら登るとそこには踊り場――屋上の入り口が六畳分ほど広がっていた。
そこなら誰もいないということを知っていた。
だから来た。
けれど、そこには残念なことに、先客がいた。
だけど幸運なことに、それがセンパイだった。
猫背で、丸くなって絵を書いていた画家さんが、そこにいた。
彼は目を薄く開いて肩で息をする私を冷たい視線で見据えていた。