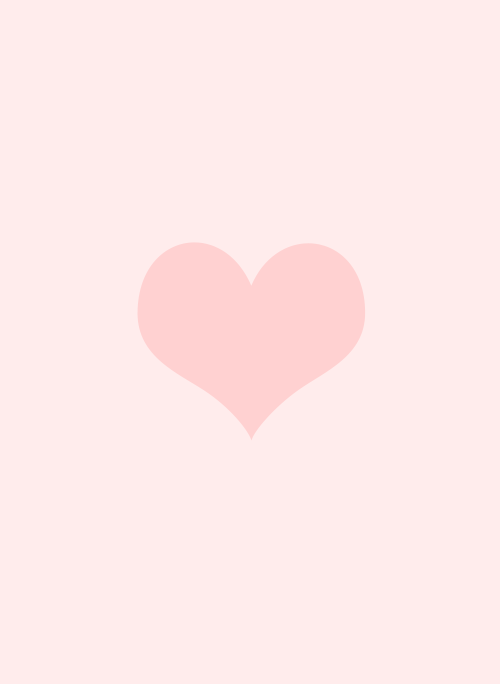それからひと月。
学校が始まって、経った。
センパイを見かけることはなかった。
もちろん、私は頻繁に屋上の入り口、いつもの場所に訪れていたけど、センパイが来た形跡すらなかった。
学校にも、来ていないのかもしれない。
私が、告白をしたから?
ぬるま湯に浸かっているような、身体がじんわり温かくなるような心地よさを、センパイは気に入っていたんだと思う。
――それを、私は壊してしまったのだ。
私は、もうこの場所にきてはいけない。
たとえ来たくても。センパイが来るかもしれないと分かっていても。
私はきっと、過去の自分と決別する時間が来てしまったのだと、そう自分自身に言い聞かせるように鳴った。
心が壊れそうなぐらいに、つらい日々が始まった。
それは、センパイに会う以前の私よりも、もしかしたら苦しんでいたのかもしれない。
そんな毎日は、単調な生活だった。
センパイと会わない、それだけで心が餓死してしまいそうだった。
そんな日が、ひと月続いて。
学校中の生徒がざわめく日が近づいた。
バレンタインデー。
センパイに会えないかもしれない……いや、会えないだろう。
そう、分かっていても、彼に贈るためのチョコを一週間前から用意しようと決めていた。
そして、バレンタインデー当日。
スクールカバンと一緒に、小さな紙袋に入れた、センパイへの愛を込めたチョコレートを大事に持って学校に向かっていた。
バスを降りて、ふと顔を上げると、雪の精が舞い降りていた。