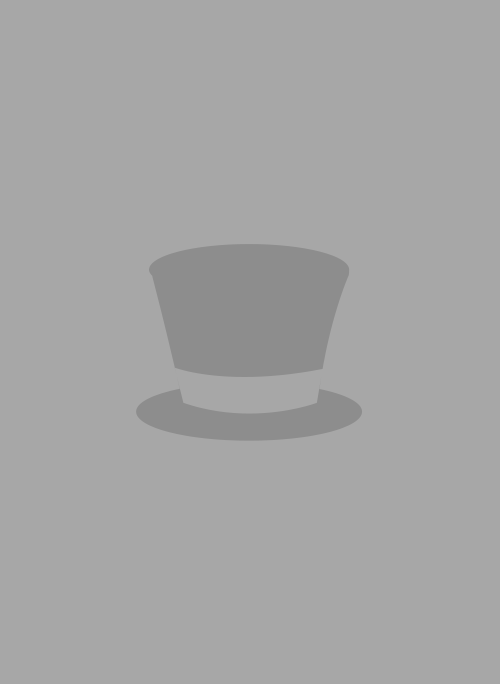「おかしいって…何が?」
「俺の体だ」
颯の体を改めて見てみる。非常に精巧に作られたアンドロイドで、遠目に見ても、いや、近くにいても、アンドロイドだと言われなければ人間だと思ってしまう。触った感触だって人間そのもので、きちんと体温まである。
「機械にしては、俺はあまりにも人間に近すぎる」
「そこまで科学技術が進んでるってことじゃないの?」
私が言うと、颯はため息をついた。
「機械が存在する理由は、何だと思う?」
すぐには答えられなかった。それでも少し考えて、答えを出してみた。
「…生活を便利にするため…?」
「ああ。じゃあ、生活を便利にするには機械にはどういうことが求められる?」
一つ質問に答えると、また一つ質問が飛んでくる。しばらくの間、私の頭は休んでいられなさそうだ。
「えっと…人間にはできないことができて、休まなくてもよくて、無駄な動きとか無駄な部品とかがなくて…」
「そこだ」
遮るように、颯は言い放った。
「機械には、無駄な部分はない。何もかも、必要なものだ」
颯がメガネを外し、右目に人差し指を当てた。そしてその指を、私に見せた。
「…」
その指は…少し、濡れていた。目に当てて濡れたんだから、きっとこれは、涙…。
「涙…? これって…」
再び、電撃が私を駆け抜けた。
「俺の体だ」
颯の体を改めて見てみる。非常に精巧に作られたアンドロイドで、遠目に見ても、いや、近くにいても、アンドロイドだと言われなければ人間だと思ってしまう。触った感触だって人間そのもので、きちんと体温まである。
「機械にしては、俺はあまりにも人間に近すぎる」
「そこまで科学技術が進んでるってことじゃないの?」
私が言うと、颯はため息をついた。
「機械が存在する理由は、何だと思う?」
すぐには答えられなかった。それでも少し考えて、答えを出してみた。
「…生活を便利にするため…?」
「ああ。じゃあ、生活を便利にするには機械にはどういうことが求められる?」
一つ質問に答えると、また一つ質問が飛んでくる。しばらくの間、私の頭は休んでいられなさそうだ。
「えっと…人間にはできないことができて、休まなくてもよくて、無駄な動きとか無駄な部品とかがなくて…」
「そこだ」
遮るように、颯は言い放った。
「機械には、無駄な部分はない。何もかも、必要なものだ」
颯がメガネを外し、右目に人差し指を当てた。そしてその指を、私に見せた。
「…」
その指は…少し、濡れていた。目に当てて濡れたんだから、きっとこれは、涙…。
「涙…? これって…」
再び、電撃が私を駆け抜けた。