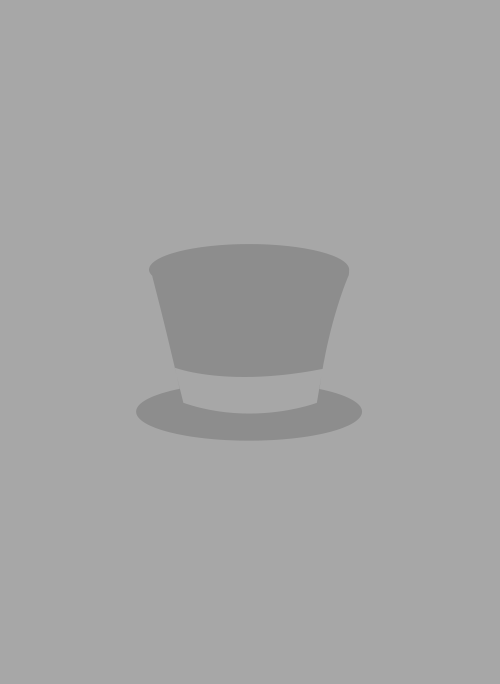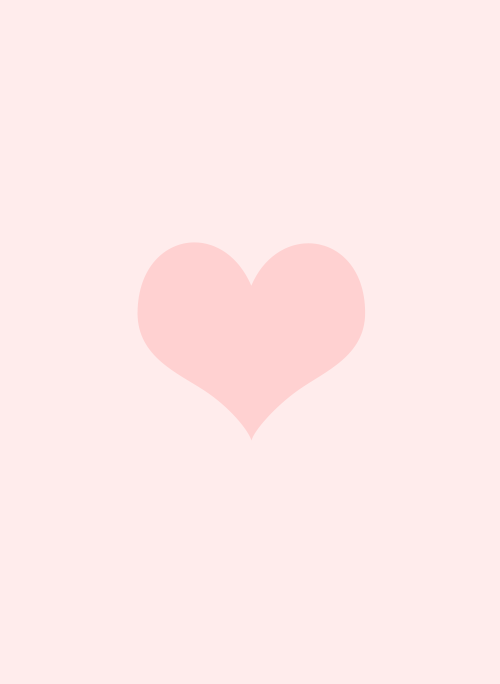「繰り返すようだが、俺には感情がない。何かを思うということがない。だから、厳密には家族になれたというのも嘘ということになる。でもあえてそれを踏まえたうえで言わせてもらうとすれば、論理的に見ても、俺は家族になれた、ということだ」
颯の手が、私の手に触れた。握ると、優しく握り返してくれた。
「…嘘じゃないよ」
何かを喋っていないと、恥ずかしい話だが、涙が出てきそうだった。
「どういうことだ?」
「颯が家族になれたっていうの、嘘じゃないよ。だって、お父さんも、お母さんも、私も…颯のこと、家族だって思ってるから」
「…嘘はついていないか?」
「私が言うより、颯が見て自分で判断する方が説得力あるよ。颯は…正直者だもん」
「正直? 俺がか?」
「颯は、嘘をつけないでしょ?」
ダメだ。喋っていても、目から頬に滴が伝っていた。
「…泣いてるのか?」
「べ…別に、深い理由とかはないよ?」
違う。深い理由しかない。
「嘘をつくな。泣いている理由も、おおむね察しがつく」
「…バカ」
誰の視線も私達に注がれていないのが幸いだった。颯の腕が私の体に回されるのと同時に、私の腕も、颯の背中に届いていた。
「…やっぱり、颯って温かいんだね」
「理由は前も説明したはずだ。同じことを何回も言うのは効率が悪い」
「何か、本物の人間みたい」
…その言葉が、颯を動かしたのだろうか? 颯は私の体を放すと、私に耳打ちした。
「…帰ったら、話がある」
急に改まった様子で話す颯を不思議に思いながら、三人がコンビニから出てくるのを待った。
颯の手が、私の手に触れた。握ると、優しく握り返してくれた。
「…嘘じゃないよ」
何かを喋っていないと、恥ずかしい話だが、涙が出てきそうだった。
「どういうことだ?」
「颯が家族になれたっていうの、嘘じゃないよ。だって、お父さんも、お母さんも、私も…颯のこと、家族だって思ってるから」
「…嘘はついていないか?」
「私が言うより、颯が見て自分で判断する方が説得力あるよ。颯は…正直者だもん」
「正直? 俺がか?」
「颯は、嘘をつけないでしょ?」
ダメだ。喋っていても、目から頬に滴が伝っていた。
「…泣いてるのか?」
「べ…別に、深い理由とかはないよ?」
違う。深い理由しかない。
「嘘をつくな。泣いている理由も、おおむね察しがつく」
「…バカ」
誰の視線も私達に注がれていないのが幸いだった。颯の腕が私の体に回されるのと同時に、私の腕も、颯の背中に届いていた。
「…やっぱり、颯って温かいんだね」
「理由は前も説明したはずだ。同じことを何回も言うのは効率が悪い」
「何か、本物の人間みたい」
…その言葉が、颯を動かしたのだろうか? 颯は私の体を放すと、私に耳打ちした。
「…帰ったら、話がある」
急に改まった様子で話す颯を不思議に思いながら、三人がコンビニから出てくるのを待った。