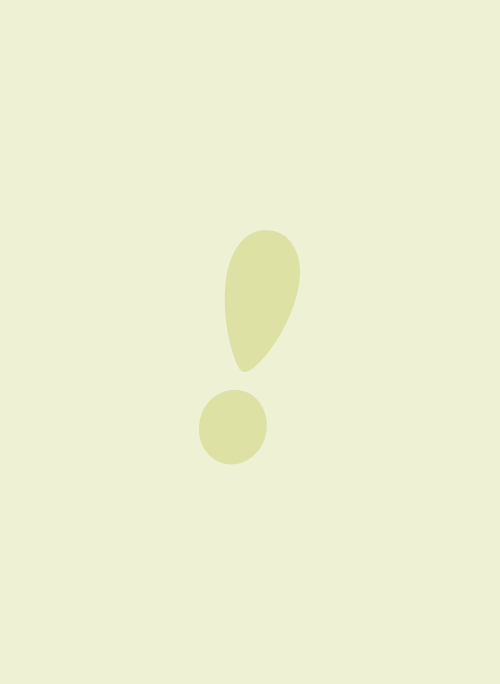あの日、颯と会った屋上での記憶が走馬灯のように蘇る。
ずっと、ずっとずっと好きで一番になりたくて。
でもそんなの叶うわけないと思ってた。
その願いが今、目の前で叶おうとしている。
夢なら一生覚めてほしくない。
確かめるように私は自分で自分の頬をつねった。
――……いっ!?
「っ!莉子!?」
告白して頬をつねる相手なんて私ぐらいだろう。
見えなくても颯が驚いているのがわかった。
「大丈夫か?」
「いたい」
「当たりま……」
「夢、じゃないんだよね?」
スカートに冷たい染みがどんどん増えてく。
頬の痛みなのか、嬉しくて泣いてるのかわからない。