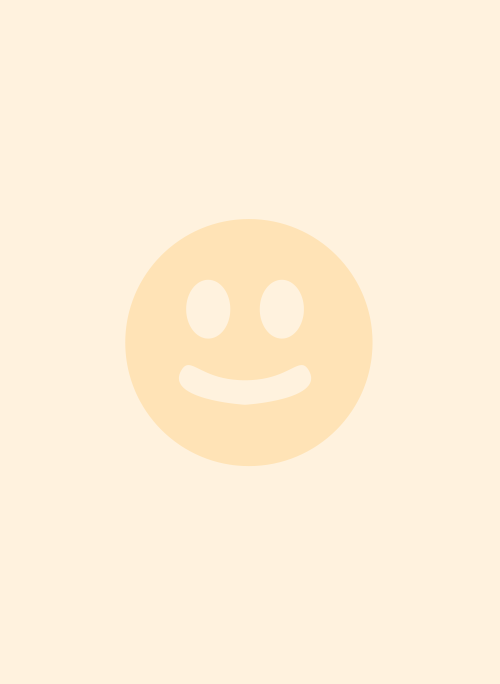「忘れるわけないだろ!」
「へ?」
いきなり叫ばれたから、今度は僕が気の抜けた声を出してしまった。
「親友のこと、忘れるなんてありえないから!その…あの時のこと、ちゃんと考えたら責任感じちゃって、来るに来れなかった…みたいな感じだから。
むしろ1日も忘れられなかったから!」
啓太の話を聞いてから、2人で泣いてた。
しばらくして、僕は右手に違和感を感じたから見てみた。
やっぱり、指が消えていってる。
もうすぐ、僕は消えるんだ。
僕が消えてしまう前に啓太に1つ聞きたいことがあった。
「ねぇ啓太、僕が消えてもずっと覚えててくる?」
やっぱり、忘れられるのが一番寂しい。
「あぁ、当たり前だろ!忘れられるわけ無い」
「よかった。」
僕がそういった時にはもう、体のほとんどが消えていた。
「約束だからね?絶対忘れないで。
それと最後に、僕、啓太と親友になれてよかった。
ありがとう。」
それを最後に、僕の体は小さな光の粉になり、溶けるように消えていった。
ありがとうの言葉を残して。
「へ?」
いきなり叫ばれたから、今度は僕が気の抜けた声を出してしまった。
「親友のこと、忘れるなんてありえないから!その…あの時のこと、ちゃんと考えたら責任感じちゃって、来るに来れなかった…みたいな感じだから。
むしろ1日も忘れられなかったから!」
啓太の話を聞いてから、2人で泣いてた。
しばらくして、僕は右手に違和感を感じたから見てみた。
やっぱり、指が消えていってる。
もうすぐ、僕は消えるんだ。
僕が消えてしまう前に啓太に1つ聞きたいことがあった。
「ねぇ啓太、僕が消えてもずっと覚えててくる?」
やっぱり、忘れられるのが一番寂しい。
「あぁ、当たり前だろ!忘れられるわけ無い」
「よかった。」
僕がそういった時にはもう、体のほとんどが消えていた。
「約束だからね?絶対忘れないで。
それと最後に、僕、啓太と親友になれてよかった。
ありがとう。」
それを最後に、僕の体は小さな光の粉になり、溶けるように消えていった。
ありがとうの言葉を残して。