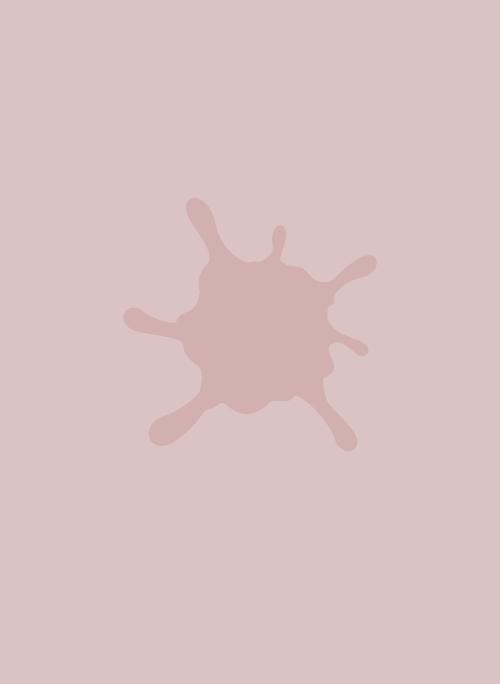朝食の後、しばらくしてボクとひとみさんは旅館をあとにした。
特に、女将さんとは、なにも特別な言葉は交わさなかった。
ただ、ボクの携帯の番号と、メールアドレスは彼女に伝えておいた。
稲取から熱海方面に向かい、ボクはのんびりと車を走らせた。
「ねぇ、ひとみさん、女将さんのこと、いつ気付いたの?」
ボクは彼女に尋ねた。
ひとみさんはタバコをくわえながら、外の景色を眺めていた。
「昔ね、公平ちゃんに写真見せてもらったことあったの、結婚式の。だから最初に旅館に着いた時ね、なんか見たことある人だなぁって、思ってたわけ。そしたら、公平ちゃんの名前が出たじゃない。その時さ、思い出しちゃったわけよ。でも、まさか、駿平君に名乗り出るとは思わなかったからさ、キミにはなにも言わなかったんだけどね」
煙をゆっくり吐き出しながら彼女は言った。
「へぇ、意外にひとみさんて鋭いんですね」
ボクの言葉に彼女は鋭い視線を向けた。
「『意外』って言葉はいらないっての!」
夏の終わりの日差しと風を受けながら、ボクらのドライブは続いた。
バカなことを言って笑いながら、走り続けた。
ひとみさんと時間を過ごすことが、いつのまにか、ボクにとって、大切なことに変わっていった。
こんな時間がこれからもずっと、当たり前のように続いていくとその時ボクは信じていた。