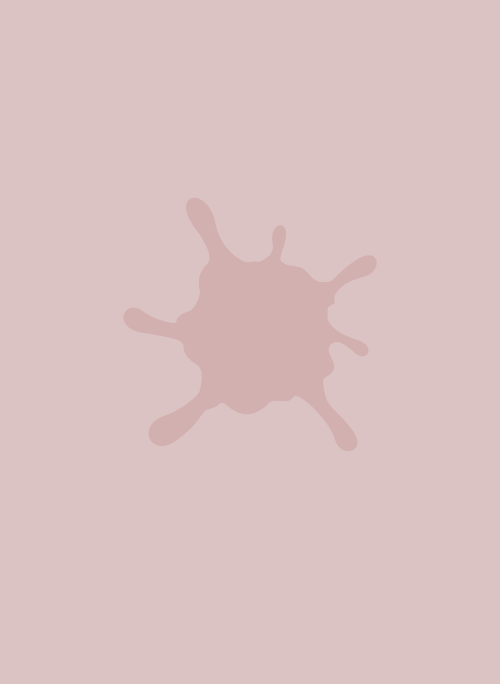ボクは無意識のうちに、ひとみさんの手をつかみ、その華奢な体を自分のもとへ引き寄せた。
彼女は驚いたように、短い悲鳴をあげた。
「しゅ、駿平君」
ひとみさんはボクの腕の中で戸惑った表情を浮かべた。
「いつまでも、いつまでも、ボクのそばにいてください、ひとみさん」
ボクは腕の中の彼女の瞳を力強く見つめながら言った。
「ありがとう、駿平君、でも、本当に私みたいな女でいいの?」
彼女はまた俯いて、ボクから視線を逸らした。
その言葉はボクの心を逆撫でした。
「あぁ?今さらウダウダ言ってんじゃねぇよ!後悔したくないから、今、あなたはここにいるんだろ!」
思わず口から飛び出した乱暴な言葉に、ひとみさんも、そしてボク自身も驚いた。
そして、もう一度彼女に向かい言った。
「ボクは、ひとみさん、アナタが好きなんだ!最初から、歳のことだって、父のことだって、全部分かってて、アナタのことを好きになったんだ!」
ボクは大きく息を吐いた。
ついに、言ってしまった。
自分の気持ちをハッキリと。
「だから、そんなこと気にする必要なんかどこにもありません!それに、アナタだってここに戻ってきたのは、自分の気持ちを伝えるためでしょ?ボクはすべてを受け止めますから」
彼女は驚いたようにボクを見上げた。
「だから、ずっとここにいてください、ひとみさん」
そう言い終わって、ボクは心からの笑顔を彼女に向けた。
彼女も、今まで見せたことがないような、心からの笑顔で応えてくれた。
ひとみさんの頬を一筋の涙が伝わった。
ボクは、その涙の流れた頬に、そっと唇をつけた。
それは、無意識の行動だった。
いや、本能だったのかもしれない。
その涙は、少ししょっぱい味がした。
ひとみさんは再び、ボクに向かい優しく微笑んだ。
そして、そっと瞳を閉じた。
ボクは彼女の唇に自分の唇を重ねた。
それは柔らかく、甘美で、少しだけ涙の味もした。
ボクは何度も何度も繰り返し、彼女の唇に自分の唇を重ね続けた。