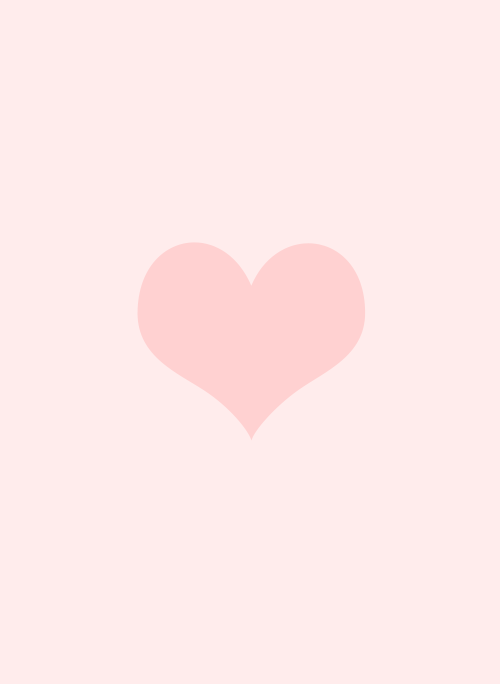鬼ごっこが終わり、私と陛下が孤児院を出たのは5時をまわったころ。
いつの間にかソラの姿は消えていて、陛下は「余計な気を…」と眉間にしわを寄せていた。きっと帰ったら怒られるに違いない。
「そういえばなんであんなに早く孤児院に来たの?」
私はふと思ったことを尋ねる。ちゃっかり鬼ごっこに参加していた陛下はすごく生き生きした顔をしていた、気がした。無表情だから分かりにくいけど、目が獲物を追う目になっていた、と思う。
2時間におよぶ鬼ごっこの後、誰もが疲労で息を乱し汗だくになっているというのに、息を乱さずそれどころか若干汗をかいていた程度で済んでいた陛下は鉄人なんだと思う。
ちなみに汗をかいているのに汚く見えず、むしろ色っぽく見える陛下には死角がないのだろう。ほんと、美形って羨ましい。
「今日、お前は迎えの時間を言って出なかっただろう」
陛下の当然の答えに私は自分の言動を振り返ってみた。確かに私は迎えをお願いする時間を言わずに出てきた。
「ごめんなさい…。それで早めに来てくれたんだ」
「…早い分には待てば済むからな」
なんて良い人なんだろう。 会って3日目の人間にそんなこと言える人が何人いるか。
…鉄人じゃないです、ごめんなさい。
心の中で謝っておく。
「ありがとう」
「…お前にそのように言われることなどしていない。余が勝手にしていることだ」
陛下は前を見据えたままをそう言う。陛下の一歩後ろを歩く私には陛下の顔が見えない。
「でも私は…この国に来て毎日がすごく楽しいから。まだ3日目だけど…本当に、楽しいの。だからありがとう」
陛下の返事はなかった。元々おしゃべりな人ではないし、この沈黙は嫌いじゃないから気にしない。
私が外出していることはお城の人たちには内緒。だから陛下も馬車で迎えには来ないけど、私は密かに陛下と歩くこの帰路が嫌いじゃない。
「でも無理はしないでね。お仕事が忙しければ私も手伝うし…というか、今更だけど“お嫁さん”がやるべき仕事もあるよね?手伝わなくて良いの?」
当たり前だけど、今の“お嫁さん”とは妃のこと。妃の公務だって当然あるはずだ。けど陛下は何も言わずに私を遊ばせてくれる。
妃に仕事があるならそれをこなすのは私の役目だ。陛下の負担になっているのならなんとかしなくちゃ。
「…特にない」
「でも…」
ああ、そうか。多分まだ私は警戒されているのだ。ていうか、いずれシャーレットに帰る人間にセレストの内政について記された書類を見せるわけにはいかないのは当たり前だ。
国王として、そういうところを徹底しないはずがないのだ。
「…手伝えること…は、ないかもしれないけど、愚痴くらいは聞くからね」
私にできることなんてこのくらい。陛下にはたくさんお世話になっているのに。私ってば役立たずも良いとこだ。これじゃあ“穀潰し王妃”なんて陰口叩かれても文句は言えない。まだ誰にも言われてないし、まだ誰も私が妃だなんて知らないんだけど。
「なら聞いてもらおうか。…うちの嫁がじゃじゃ馬過ぎて困る」
「うっ」
「落ち着きはないし、寝相は悪いし、放っておくと髪が濡れたまま寝ようとするし、寝癖がついたまま出かけようとするし」
「ソ、ソレハ、タイヘンデスネ…」
ああ。穀潰し王妃どころの騒ぎじゃない。もう陛下にとっては害悪でしかない。害悪王妃だ。どうしよう。
「…だが…最近、随分と部屋が賑やかになった。前よりも深く眠れるようになった。…朝起きると腕の中に間抜けな寝顔があるから、朝が来るのが楽しみになった」
私って単純な生き物だ。決して褒められてるわけじゃないのに、陛下に“この国にいても良い”って言われてるみたいで嬉しい。こんな言葉でも私はスキップしたくなるくらいに嬉しい。
「不意打ち、ずるい」
暗くてよかった。今、私の顔は赤い。赤くなる要素なんてないのに顔が熱いのだ。
きっと相手が陛下だからだ。いつも眉間にシワを寄せて嫌味を言う陛下にそう言われたから嬉しいんだ。
ーそれはお互い様だ
そんな返事が聞こえたような気がしたけどきっと気のせい。私の耳は都合よくできてるから、気のせいに違いない。
「この国にいる間に、絶対貴方の女子力吸収してやるから!貴方の悩み、私が解決するから!」
照れ隠しに私はそう叫んだ。
“女子力じゃない”そんな言葉と共に陛下に頬を引っ張られたからきっと顔が熱いのがばれたと思う。
けど不思議と頬は痛くなかった。陛下上手だ。