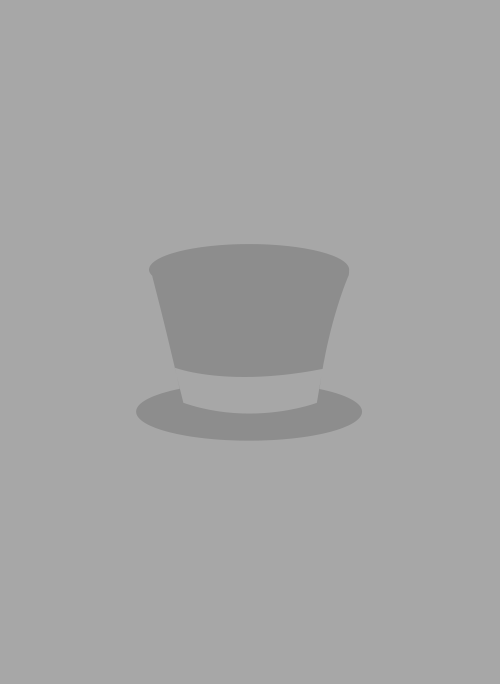僕はそういう気は全くと言って無いのだが...。
「ぼくはちょっと不幸な、其れで律儀な...そんな、つまらない女なんだよ。」
「知ってる。」
顔を伏せているのか、後頭部にルルの吐息がかかる。
「生理前かい?」
「デリカシーの無い奴は嫌いだ...。」
せめて気遣いがあるって言って欲しいな。
「良く効く痛み止め有るけど如何かい?」
「何で持ってんの?」
「紳士だろ?」
子供の中には、生理痛が有る子がいるから、持っているんだけどね。
高感度が下がるな...。
「だから気持ち悪いんだよ。化け物...。」
「君にしては安直な暴言だな。」
「化け物に、化け物って言って何が悪い...。化け物...。」
ルルにしては弱々しい声だ。
「君さては、嫌な事があったな!
其れで僕に甘えてきたのか!?」
「...違うし......。」
図星だ。
右足が痛いって言うのは、嘘の口実...。
嗚呼、ルルらしい。
義足を一通り見ても、特に異常が無い筈だ。
「話を聞いてあげようじゃないか。
君が嫌いな化け物が。」
「そんな、嫌ってない...。」
「はい、はい。何があったんだい?」
ルルは視線を下げて、口篭りながら口を開き始めた。
「母様(かあさま)が死んだ夢...。心電図が波を打たなくなって、ピー、ピーって電子音が室内に響き渡る。そんな夢...。
怖かった。死んでしまう程怖かった。
母様が死んだら...“あたし”...、」
母親関係か...。
ルルは僕と違って母親が大好きで大切なんだ。
命よりも大切で尊い者なんだ。
対して僕は、母親が嫌いだ。最初は、生きていく上で仕方無く一緒にいたが、僕を正確には僕達兄弟をあの施設にやってから、僕は絶対彼奴等を殺すと心に決めた。
そして、実行に移した。
其れは其れは今までに無い最高の笑顔で殺してやった。
殺してあげた。
だが、ルルは違う。
本当に心から愛しているんだ。
僕には何年経ったって、理解出来ない尊い感情をルルはずっと持っている。
羨ましいと思う反面酷く妬ましかった。
如何して僕は理解する事が出来ないのだろう。僕の探究心は嘆いている。
ルルに退ける様肩を静かに叩いた。ルルが退くと、僕は隣に着いた。
瞳が潤んでいるのがよく解る。
涙ぐむルルの頭を撫でながら、胸を貸した。
「安心しな。君の母親は死んでない。
其れは君がよく知っているじゃないか。」
「だけど...何時、死んじゃうか解らないだろッ!」
生身の右手で僕の胸板を叩く。
痛くはないが衝撃は伝わる。
「人は何時か死ぬさ。其れを君が嘆く事は無い。
君は精一杯やり遂げている。
...気が晴れないなら、幾らでも僕を頼ると良いさ。」
「...ちょっと、黙ってて。」
「はい、はい、仰せのままに。」
ルルは、彼女は僕の白衣の襟を握り締めて、胸に顔を埋めた。
彼女は稀に、堰を切ったように、僕に泣きつく。僕だけの特権みたいな感じがして、少しばかり嬉しい気がするのは、彼女には黙っておこう。
強気な女の子に泣きつかれるっては、これまた男として嬉しいじゃないか。
其のままベッドに連れて行きたいのは、やまやまだが嫌われるのは嫌だから連れて行かない。
僕にしては珍しく、女性に対して気を遣う。
「誰にも言うなよ...」
落ち着いたルルが、顔を上げずに呟いた。
「言わないよ。泣き虫な女の子は、そんな心配しなくて良いんだよ。」
肩をとんとんと叩いて、宥める様に言う。
「子供扱いしないでよ。ぼくは歴とした成人女性だよ。」
「僕にしては子供も同然だ。」
其れに、泣きつく時点で充分子供だ。
「たった5歳違いだろ。」
「5年も後に産まれたんだ。充分さ。」
「精神年齢は幼児と変わらない癖に...。」
子供とは良く言われるけど、幼児は初めてだな。
でも嫌だな...これでも29なんだけど。
「酷いな〜、せめて自分に素直って言って欲しいな。
て言うか、幼児は無いだろ。幼児は。」
「ハハハッ...幼児で充分だろ。あんたは。」
「酷いな〜。僕拗ねちゃうよ!」
頬をルルの髪に擦り付ける。
離れようとするルルを抱き締めて、診察台に倒れ込む。
「何で抱き締めるの?離してよ。」
「んー、何となくさ。」
「これじゃまるで、あんたと恋人みたいじゃないか。気持ち悪い。」
「アハハハッ!!僕と君が恋人!?アハハハハ!!!」
僕は大笑いした。
ルルが五月蝿そうだったが、笑いが勝った。
「恋人ねぇ...アハハ、其れは互いに愛を共有している男女を示すものだろ。
僕と君の間に愛なんて道徳的なものは存在しないだろう。」
「...そうなんだ。」
ルルは素っ気なく言った。
「え!?何?君はそう言うモノを持っていたのかい!!?」
驚いて上半身を上げた。
ルルに限ってそう言う気を、起こす事は無いと思っていたのだが...。
「持ってないよ!!気持ち悪い!!キモい!!」
「じゃ、じゃ何でそう思ったんだい?」
互いに半パニック状態になってしまっている。
だって、僕には縁の無い事だと思っていたから...。
「だってあんたが、そういう風に接するからでしょ!!!」
「はぁ?僕が?」
「仕事関係の女にこんな事するか!?普通?」
「......しない、ね。」
常識的に考えてみればそうだ。
至って普通に接していたつもりが...如何言う事だ。
最大速度で頭を動かす、安心した。僕には“愛”や“恋”なんて感情は無かった。
矢張り、やっぱり、思った通り。
僕にそんな感情は存在しない。
「ぼくはちょっと不幸な、其れで律儀な...そんな、つまらない女なんだよ。」
「知ってる。」
顔を伏せているのか、後頭部にルルの吐息がかかる。
「生理前かい?」
「デリカシーの無い奴は嫌いだ...。」
せめて気遣いがあるって言って欲しいな。
「良く効く痛み止め有るけど如何かい?」
「何で持ってんの?」
「紳士だろ?」
子供の中には、生理痛が有る子がいるから、持っているんだけどね。
高感度が下がるな...。
「だから気持ち悪いんだよ。化け物...。」
「君にしては安直な暴言だな。」
「化け物に、化け物って言って何が悪い...。化け物...。」
ルルにしては弱々しい声だ。
「君さては、嫌な事があったな!
其れで僕に甘えてきたのか!?」
「...違うし......。」
図星だ。
右足が痛いって言うのは、嘘の口実...。
嗚呼、ルルらしい。
義足を一通り見ても、特に異常が無い筈だ。
「話を聞いてあげようじゃないか。
君が嫌いな化け物が。」
「そんな、嫌ってない...。」
「はい、はい。何があったんだい?」
ルルは視線を下げて、口篭りながら口を開き始めた。
「母様(かあさま)が死んだ夢...。心電図が波を打たなくなって、ピー、ピーって電子音が室内に響き渡る。そんな夢...。
怖かった。死んでしまう程怖かった。
母様が死んだら...“あたし”...、」
母親関係か...。
ルルは僕と違って母親が大好きで大切なんだ。
命よりも大切で尊い者なんだ。
対して僕は、母親が嫌いだ。最初は、生きていく上で仕方無く一緒にいたが、僕を正確には僕達兄弟をあの施設にやってから、僕は絶対彼奴等を殺すと心に決めた。
そして、実行に移した。
其れは其れは今までに無い最高の笑顔で殺してやった。
殺してあげた。
だが、ルルは違う。
本当に心から愛しているんだ。
僕には何年経ったって、理解出来ない尊い感情をルルはずっと持っている。
羨ましいと思う反面酷く妬ましかった。
如何して僕は理解する事が出来ないのだろう。僕の探究心は嘆いている。
ルルに退ける様肩を静かに叩いた。ルルが退くと、僕は隣に着いた。
瞳が潤んでいるのがよく解る。
涙ぐむルルの頭を撫でながら、胸を貸した。
「安心しな。君の母親は死んでない。
其れは君がよく知っているじゃないか。」
「だけど...何時、死んじゃうか解らないだろッ!」
生身の右手で僕の胸板を叩く。
痛くはないが衝撃は伝わる。
「人は何時か死ぬさ。其れを君が嘆く事は無い。
君は精一杯やり遂げている。
...気が晴れないなら、幾らでも僕を頼ると良いさ。」
「...ちょっと、黙ってて。」
「はい、はい、仰せのままに。」
ルルは、彼女は僕の白衣の襟を握り締めて、胸に顔を埋めた。
彼女は稀に、堰を切ったように、僕に泣きつく。僕だけの特権みたいな感じがして、少しばかり嬉しい気がするのは、彼女には黙っておこう。
強気な女の子に泣きつかれるっては、これまた男として嬉しいじゃないか。
其のままベッドに連れて行きたいのは、やまやまだが嫌われるのは嫌だから連れて行かない。
僕にしては珍しく、女性に対して気を遣う。
「誰にも言うなよ...」
落ち着いたルルが、顔を上げずに呟いた。
「言わないよ。泣き虫な女の子は、そんな心配しなくて良いんだよ。」
肩をとんとんと叩いて、宥める様に言う。
「子供扱いしないでよ。ぼくは歴とした成人女性だよ。」
「僕にしては子供も同然だ。」
其れに、泣きつく時点で充分子供だ。
「たった5歳違いだろ。」
「5年も後に産まれたんだ。充分さ。」
「精神年齢は幼児と変わらない癖に...。」
子供とは良く言われるけど、幼児は初めてだな。
でも嫌だな...これでも29なんだけど。
「酷いな〜、せめて自分に素直って言って欲しいな。
て言うか、幼児は無いだろ。幼児は。」
「ハハハッ...幼児で充分だろ。あんたは。」
「酷いな〜。僕拗ねちゃうよ!」
頬をルルの髪に擦り付ける。
離れようとするルルを抱き締めて、診察台に倒れ込む。
「何で抱き締めるの?離してよ。」
「んー、何となくさ。」
「これじゃまるで、あんたと恋人みたいじゃないか。気持ち悪い。」
「アハハハッ!!僕と君が恋人!?アハハハハ!!!」
僕は大笑いした。
ルルが五月蝿そうだったが、笑いが勝った。
「恋人ねぇ...アハハ、其れは互いに愛を共有している男女を示すものだろ。
僕と君の間に愛なんて道徳的なものは存在しないだろう。」
「...そうなんだ。」
ルルは素っ気なく言った。
「え!?何?君はそう言うモノを持っていたのかい!!?」
驚いて上半身を上げた。
ルルに限ってそう言う気を、起こす事は無いと思っていたのだが...。
「持ってないよ!!気持ち悪い!!キモい!!」
「じゃ、じゃ何でそう思ったんだい?」
互いに半パニック状態になってしまっている。
だって、僕には縁の無い事だと思っていたから...。
「だってあんたが、そういう風に接するからでしょ!!!」
「はぁ?僕が?」
「仕事関係の女にこんな事するか!?普通?」
「......しない、ね。」
常識的に考えてみればそうだ。
至って普通に接していたつもりが...如何言う事だ。
最大速度で頭を動かす、安心した。僕には“愛”や“恋”なんて感情は無かった。
矢張り、やっぱり、思った通り。
僕にそんな感情は存在しない。