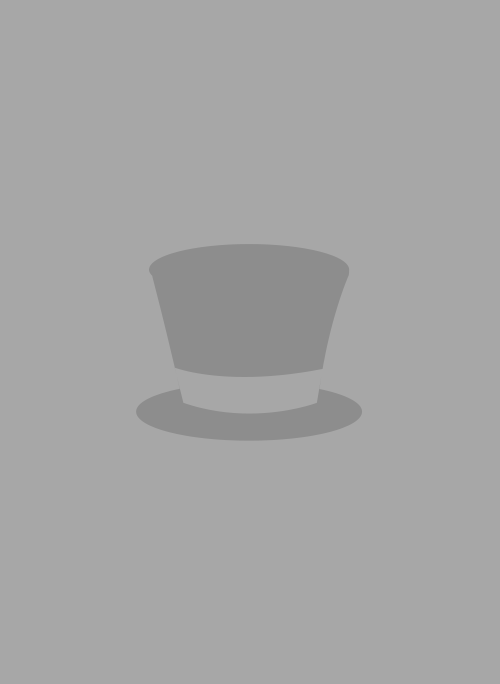ルルはまた溜息を吐いた。
溜息ばかり吐く癖はセルリアにどことなく似ていると思う。
名前を呼び間違えないかヒヤヒヤする。
「ぼくは手伝わないから。」
「はいはい、解ってるよ。そんなに念を押さなくても...」
普段から僕が巫山戯てるからって、まるで母親のように口酸っぱくして言わなくても良いじゃないか。
僕の方が年上なんだよ。こう言う事も慣れてるし...。
...まるで“母親”ね。そんな母親居なかった癖に。
「何処へ向かうんです?」
追い付いたマーソンが声を掛ける。
「取り敢えず、人気の無い場所ですよ。」
そう言って微笑んだ後、マーソンの返事を聞かずに足を進めた。
路地裏の...、奥の奥。細い道を辿って、静かな場所へ。
表から裏へ。あちらから、こちらへ。
僕達の世界へと歩を進めていく。ホームレスすら見えない。
道中マーソンは口を聞かなかった。
僕も何も言わなかった。
唯僕には、蝋の短い彼の灯火が見えている。
少々開けた場所に突き当たると、僕は歩を止めた。背後から少し押される感覚があった。
マーソンが僕の背中に鼻先をぶつけたのだろう。
特に気にはしない。
「此処で良いでしょう。人も居ないし、何より静かだ。」
「ね!」と同意を求めたが、マーソンからは苦笑しか得られなかった。
コートのポケットに両手を入れる。右手のポケットにメリケンサックが入っていた。
手に跡が付くから余り使いたくないし、殺傷力もまちまちだし...、力加減間違えたら僕の指が折れる可能性があるけど...。
贅沢言ってられないよね。
頭を狙えば良い話だし。そうだね、顔面を中心に殴ればすぐ終わるだろう。
後は汚れにさえ気を付ければ問題無いな。
「あの、早速ですが...」
「スレッド・マーソンさん!!!」
振り向き様にフルネームを言うと、彼は体を強ばらせて黙った。
「な、何でしょう...?」
「いえ、呼んでみただけです。」
マーソンの周りを旋回しつつ、僕は言葉を続けた。
舞台に立つ役者のように、大袈裟な身振り手振りを付けて...。
「“痛み”とは、素晴らしいモノだと思いませんか?」
突然の質問にマーソンもルルも疑問詞を口にした。
「時に危機を知らせ、身を守り。自身の死の足音を告げてくれます。
...そうでしょう?」
一回転回る。コートの裾がスカートのように広がった。
「しかし!“痛み”と言うのは、人に嫌われている。当たり前だ。誰しも痛みなど好まない。
待てよ...これは語弊があるな。
...一般的に好んでいる人は居ません」
そうだ。これが近い言葉だ。
徐々にマーソンが警戒し始めた。
両手はまだ、ポケットの中だ。
「だが、僕は...、其れを愛おしく恋焦がれている。欲しくて欲しくて、堪らない。
これは決して僕が例外に当てはまる訳ではありません。
いや、ある意味例外かも...」
左手を口元に添える。
ほんの少し目を開いて、わざとらしく感心した。
再び左手をポケットに戻し、そっと口角を上げ薄く微笑んだ。
「マーソンさん。貴方は信じますか?
“痛み”が無い事を、死を実感できない事を...」
「は、はぁ?」
返ってきた返事は気が抜けそうな声だった。