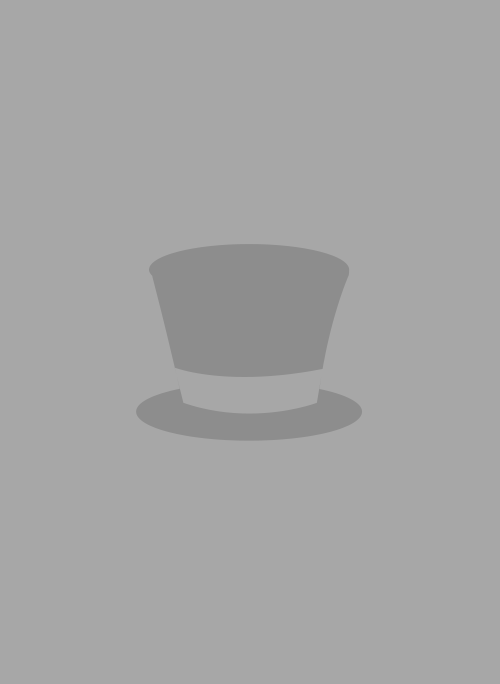マーソンの表情が引き攣る。
僕の笑顔に何かしらを感じたのだろう。
呆れたと言いたげなルルの溜息も聞こえる。
「さて、何を聞きたいんです?」
殺気は出していない。
こんな些細な事で殺気を漏らすだなんて、この仕事をやってられないよ。殺気の無い殺意こそ最も恐ろしい刃だ。
其れを持っていないとすぐ殺られる。
ルルが不意に爪先で音を鳴らした。
妙にリズムを刻むその音が、モールス信号だとすぐに解った。
“あんた...時間は良いのかい?”
僕も爪先で返事をした。
“良いんだよ。ここからが面白いんだからさ。
さぁ、彼は自身の寿命をどれだけ延ばせるのかな?”
ルルに視線を流して、瞳を細くし微笑んだ。
眉間に皺を寄せられ睨み付けられてしまった。
そんなに怖い顔をしなくても良いと思うんだけどな。
ルルなりに思う所があったのだろう。ドジは踏まないよ。僕は馬鹿じゃないからね。
「では、お言葉に甘えて...。【S】の人間関係の中で、親しい間柄の方はスレイマさん。貴方しか居ないのでしょうか?
他の有名な画家の中で友好関係があれば知りたいのですが...。」
「画家の中では居ないでしょう。だからこそ彼は謎に包まれていたのですからね。
其の他でしたら、それなりに居ると思いますよ。」
馬鹿か...。其れ位解るだろ。
笑顔を崩さずに僕は記者を罵る。
さぁ、さぁ、もっと話を盛り上げて続けないと、貴方の命はすぐに消えてしまうよ。
命を握っているのは僕なんだから...。
珈琲を一口飲んで、マーソンの眼を見据えた。
マーソンは刺さる僕の視線に居た堪れないようだ。
「そうですか...。恋人、とかは居ますかね?」
「いや、彼には居ませんよ。
そうですね...妹なら居ました。」
恋人なんて笑える。どう頑張っても出来るわけないじゃないか。
何せ彼だよ。
「妹か...。彼女の所在などは?」
「マーソンさん。ちゃんと聞いてましたか?
僕は“居ました”と言ったんですよ。」
「...、すいません。」
申し訳なさそうにマーソンは頭を下げた。
下げるべき相手は僕では無いだろう。そもそも血縁者が死んだ所で、其れが何だと言うのだ。
残念ながら、僕に其の心理は解らない。
知る事は出来ても、理解する事は出来ない。
「良いですよ。僕は彼じゃありませんし...。ですが、今だに彼は彼女に取り憑かれてますよ。」
あっ...、口が滑ってしまった。
一瞬だけ目を見開いた後、表情を戻した。
まぁ知られなければ何か言われる事もないよね。
「は、はぁ...。あっ、そう言えばまだ聞いてませんでしたね。
【S】の本名は、何ですか?」
「其れは...、」
其れは...流石に言えないななぁ。
珈琲を飲み干して、席を立った。マーソンが怪訝そうな顔で僕を見ている。
「人気の少ない場所で話しましょう。多くに知られる訳にはいかないので...」
「...はぁ」
ここから先を聞いたと言う事は、記者の命のタイムアップを告げた事と同じだ。
もっと話が出来ると思ったんだけどな...、矢張り詰まらないものは、詰まらないものだった。
其れに加え、瞳も綺麗で美しくも無い。正直時間を棒に振ったようなものだ。腹立たしいな...、原型が無くなるまでグチャグチャにしてあげないと、気が収まらないね。
速やかに会計を終え、喫茶店を出る。
僕の持ち物の中では、僕の好きな“やり方”は出来そうにない。これもまた不服なのだが、贅沢を言ってられない。
マーソンと少し距離を置いて、足を進める。隣りでルルが小声で声を掛けてきた。
「殺るなら手短にしなよ...。」
「えっ!?何?心配してくれてるの...?」
「アンタは遊びそうな気がしたんだよ。ぼくに其の趣味は無いから、止めて欲しいだけ。」
「安心してよ...彼奴嫌いだから、すぐ終わるよ。」
「期待はしないでおくよ。」
「相変わらず冷たいな...。」
「此処に居るだけ優しいと思ってもらいたいね。」
僕の笑顔に何かしらを感じたのだろう。
呆れたと言いたげなルルの溜息も聞こえる。
「さて、何を聞きたいんです?」
殺気は出していない。
こんな些細な事で殺気を漏らすだなんて、この仕事をやってられないよ。殺気の無い殺意こそ最も恐ろしい刃だ。
其れを持っていないとすぐ殺られる。
ルルが不意に爪先で音を鳴らした。
妙にリズムを刻むその音が、モールス信号だとすぐに解った。
“あんた...時間は良いのかい?”
僕も爪先で返事をした。
“良いんだよ。ここからが面白いんだからさ。
さぁ、彼は自身の寿命をどれだけ延ばせるのかな?”
ルルに視線を流して、瞳を細くし微笑んだ。
眉間に皺を寄せられ睨み付けられてしまった。
そんなに怖い顔をしなくても良いと思うんだけどな。
ルルなりに思う所があったのだろう。ドジは踏まないよ。僕は馬鹿じゃないからね。
「では、お言葉に甘えて...。【S】の人間関係の中で、親しい間柄の方はスレイマさん。貴方しか居ないのでしょうか?
他の有名な画家の中で友好関係があれば知りたいのですが...。」
「画家の中では居ないでしょう。だからこそ彼は謎に包まれていたのですからね。
其の他でしたら、それなりに居ると思いますよ。」
馬鹿か...。其れ位解るだろ。
笑顔を崩さずに僕は記者を罵る。
さぁ、さぁ、もっと話を盛り上げて続けないと、貴方の命はすぐに消えてしまうよ。
命を握っているのは僕なんだから...。
珈琲を一口飲んで、マーソンの眼を見据えた。
マーソンは刺さる僕の視線に居た堪れないようだ。
「そうですか...。恋人、とかは居ますかね?」
「いや、彼には居ませんよ。
そうですね...妹なら居ました。」
恋人なんて笑える。どう頑張っても出来るわけないじゃないか。
何せ彼だよ。
「妹か...。彼女の所在などは?」
「マーソンさん。ちゃんと聞いてましたか?
僕は“居ました”と言ったんですよ。」
「...、すいません。」
申し訳なさそうにマーソンは頭を下げた。
下げるべき相手は僕では無いだろう。そもそも血縁者が死んだ所で、其れが何だと言うのだ。
残念ながら、僕に其の心理は解らない。
知る事は出来ても、理解する事は出来ない。
「良いですよ。僕は彼じゃありませんし...。ですが、今だに彼は彼女に取り憑かれてますよ。」
あっ...、口が滑ってしまった。
一瞬だけ目を見開いた後、表情を戻した。
まぁ知られなければ何か言われる事もないよね。
「は、はぁ...。あっ、そう言えばまだ聞いてませんでしたね。
【S】の本名は、何ですか?」
「其れは...、」
其れは...流石に言えないななぁ。
珈琲を飲み干して、席を立った。マーソンが怪訝そうな顔で僕を見ている。
「人気の少ない場所で話しましょう。多くに知られる訳にはいかないので...」
「...はぁ」
ここから先を聞いたと言う事は、記者の命のタイムアップを告げた事と同じだ。
もっと話が出来ると思ったんだけどな...、矢張り詰まらないものは、詰まらないものだった。
其れに加え、瞳も綺麗で美しくも無い。正直時間を棒に振ったようなものだ。腹立たしいな...、原型が無くなるまでグチャグチャにしてあげないと、気が収まらないね。
速やかに会計を終え、喫茶店を出る。
僕の持ち物の中では、僕の好きな“やり方”は出来そうにない。これもまた不服なのだが、贅沢を言ってられない。
マーソンと少し距離を置いて、足を進める。隣りでルルが小声で声を掛けてきた。
「殺るなら手短にしなよ...。」
「えっ!?何?心配してくれてるの...?」
「アンタは遊びそうな気がしたんだよ。ぼくに其の趣味は無いから、止めて欲しいだけ。」
「安心してよ...彼奴嫌いだから、すぐ終わるよ。」
「期待はしないでおくよ。」
「相変わらず冷たいな...。」
「此処に居るだけ優しいと思ってもらいたいね。」