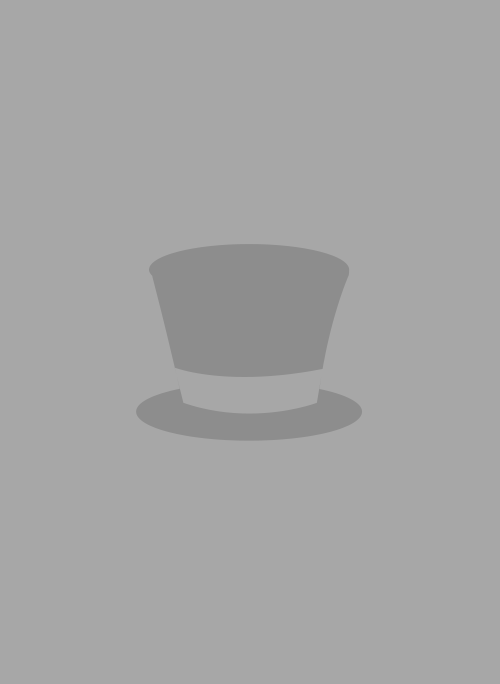side:ギフト
記者スレッド・マーソンと共に絵画展からそう遠くない喫茶店へと足を運んだ。
昼時と言うのもあって、少々混んでいたが1番奥の目立たない席を奇跡的に取る事が出来た。
僕、ルルと順に座り、向かいにマーソンが座る。店員に珈琲2つとココア1つを頼んだ。
「本題に入っても...?」
「僕は構いませんよ。後で友人の家に行く予定なので、出来るなら早く終わらせましょう。」
ルルに横腹をど突かれた。「聞いてない」とでも言ったのだろう。
当たり前だよ。言っていないんだもの。言ったらルルは絶対着いて来ないし...。
今回の要はルルだからね。帰らせる訳には行かないんだ。
「そうでしたか...。では、早速...、単刀直入に聞きますが、【S】とはどんな人物なんですか?」
「どんな、ですか...。そうですね。まずは性別から言いましょう。【S】は男性です。」
「男性だったのですか!
繊細な絵柄から女性と思っていましたが...。」
「繊細ね...、まぁ彼もそんな所があるんじゃないでしょうか。」
普段のガサツさを見慣れているから、笑いが込み上げてくるよ。
まぁでも、“彼女”に関しては確かに繊細かもね。
「次は何を答えましょうか。」
「では、彼の趣味とか、どんな性格とか?
些細な事で良いので...、何せ【S】は謎が多くてね。」
「彼を知っている僕からすれば、謎なんて無いんでね。」
あれ、これ何時もの僕と変わらない気がするな。
良いか。変に勘づかれたら殺せば良いし。
処理はアヴァンに頼もうか。腕は良い、仕事は早い。セルリアの使用済みの何かしらをあげれば、まけてもらえるだろう。
彼女はセルリアにお熱だからね。
「そうだな...彼は結構ガサツな性格なんですよ。その割りに妙に勘が良い所がありまして...、彼のそんな所が画家としての才能に繋がったのではないでしょうか?
まぁ僕は芸術に乏しいので素人の感想ですけど...」
澄み切っているより少々濁っている方が、人は信じ易い。
何せ日常と言うモノは濁っているからだ。だから、澄み切った綺麗な言葉を疑う。
勿論、全員がそういう訳では無いよ。
そういう人が多いって話。
虚偽を混ぜた真実はより真実味を増す。
このスレッド・マーソンを僕の駒にする為に、僕は虚偽入りの真実を飲ませるのだ。
良心が痛まないのか、と聞くのかい。
済まないね。
痛む良心が無いんだよ。
マーソンは記者として、僕の発言をメモに書き留めている。
記者は嫌いだ。忘れない様に気を使っているし、奥深くまで探求してくるからだ。
諸事情により記者は何度か殺してきた。どの記者も最期まで、情報を残そうと執拗に手掛かりを残したものだ。
消すのに手を焼いたよ。
「彼の所在を知っていますか?」
「...え、あっ...、今なんと?」
マーソンの質問に上の空だった僕は思わず聞き返した。
「...彼のアトリエを知っていますか?」
「アトリエですか...」
そこを聞いてしまうのか。
矢張り、記者は嫌いだ。
嗚呼好奇心さえなければ、長生きできただろうにな。
「えぇ、知ってますよ。
住所を書きましょうか?」
「是非!」
マーソンは快く僕に手帳を渡した。
手帳を受け取り“本当”の住所を書いて、マーソンに返した。
「詳しくは僕より本人に聞くといい。
実際に行ってみてはどうです?展示会の〆切を終えた今なら、彼にも余裕があるでしょう。」
「後で伺ってみます。
今は貴方から聞ける【S】についてもっと知りたいです。」
「...僕から聞ける、ね。たかだか友人ですよ。
其れで良ければ話しましょう。」
僕は笑顔で言う。笑顔は良い...笑顔は人にしか出来ないから。
笑顔は良い印象も悪い印象も等しく同時に与える事が出来るから。