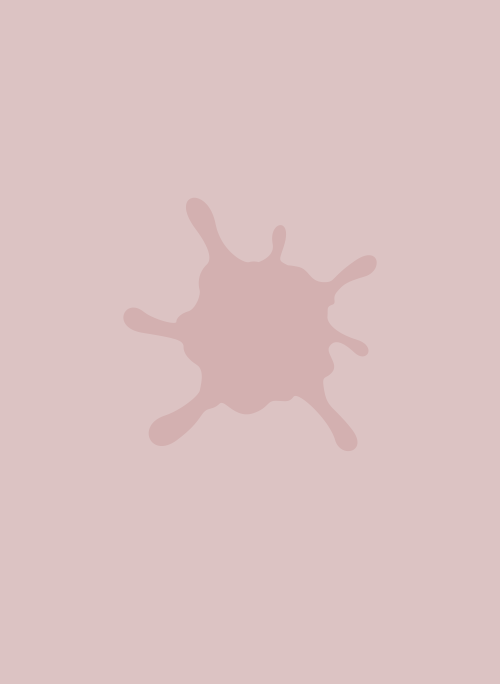「やっぱり面白い」
「よく言われる」
僕は彼女に微笑んだ。
煙草の火を消した。
シュッと小さい音が聞こえる。
沈黙の空間にはうるさい音。
ツバキは立ち上がった。
ベットの横についているコンポに手を伸ばす。
流れてきたのはクラシックだった。
少しして僕は気が付いた。
この曲は、ここに来る前に車の中でラジオから流れた音楽。
僕が好きなメロディ。
「ツバキさん」
「何?」
彼女は再びベットに戻った。
「この曲知ってる?」
「知ってるわ」
「いい曲だなって思って」
「なんか珍しい」
「珍しい?」
僕は天井から目を落とし彼女に目を向けた。
「だって、全く今まで何にも興味を示さなかったじゃない?」
「そう?僕たち短い時間しか付き合ってないけど」
「だいたいわかるわ。私は貴方より生きてるもの」
彼女はそういうと僕に意味ありげに微笑んだ。
なんの根拠もない言葉だったけど、確かに僕より生きている。
僕より大人だ。
僕が思う大人は、自ら生きている人のことを示す。
生かされている人は子供だ。
だからいくら体だけが成長しても子供のまま。
僕もまた子供。