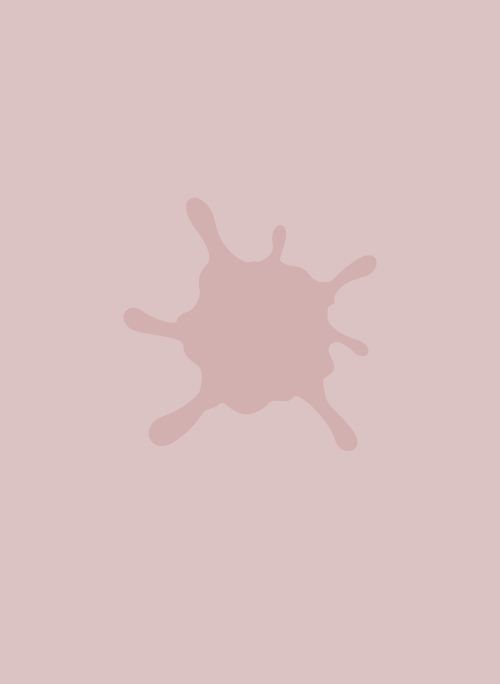僕の知ってるマスターはあの白髭の優しい笑顔のおじさんだ。
僕の知らない世界で、若い男性がマスターだなんてなんて虚しい話だ。
彼女はそのマスターと知り合いのようだった。
僕には見せない表情で彼と話している。
少しして僕の前に、彼の手と同時に円錐形で足と台がついた薄手の小形グラスが置かれた。
「スカイダイビング」
「面白い名前だね」
「はじめてみるお客さんだから、誰の口にも合う飲みやすい甘口にしました」
スカイブルーの印象的なカクテル。
僕はグラスに口をつける。
「ホワイトラム、ブルーキュラソーにライムジュースをシェークして作りました。お味はいかがですか?」
「おいしい」
「それは、よかったです」
甘いマスターの声は、きっとこの店の売りでもあるだろう。
その証拠に、男性より女性の比率が高かった。
今度は彼女の前にグラスが置かれた。
彼は奥にいる客に呼ばれて、頭を下げると行ってしまった。
「ストロベリーブリュー」
彼女はグラスを持ち上げ見つめていた。
フルートグラスにイチゴが3コ入っている。
「ブリューはフランス語で“甘味をつけていない”」
「ふ〜ん」
「辛口白ワインで仕上げてあるの」
彼女は僕に顔を向けて微笑んだ。