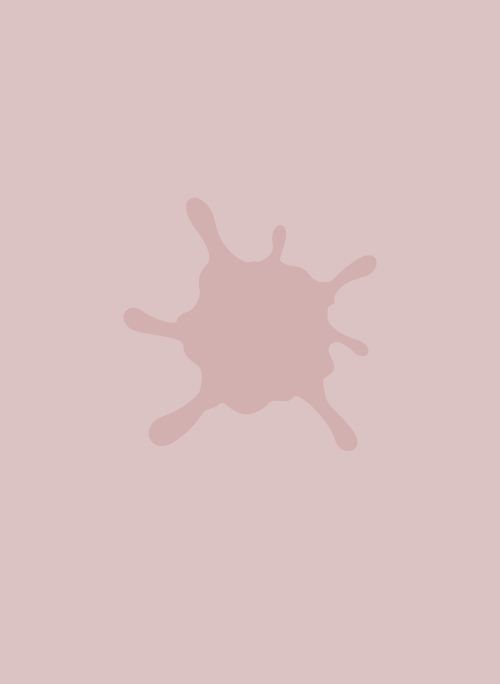ホテルから5分ほど歩くと、彼女の足が止まった。
「ここよ」
彼女は地下に続く階段を下りていく。
1階は高級レストランに見えて、本当は手頃なお値段のレストランだろう。
そう思えたのも、店の前にある看板に、本日のおすすめディナーとチョークで書かれていたからだ。
本物の高級レストランなら、そんな手間はしない。
地下につくと扉がポツンとあって、上から小さいランプで僕たち客を照らしているだけだった。
彼女が扉を押すと、チャリンと鈴の音が響く。
それと同時に奥から声が聞こえた。
「いらっしゃい」
僕はその声の主を探した。
カウンターの奥でちょうどカクテルを作っているところだった。
彼女は僕を無視してすたすたと歩き、カウンターの椅子に座った。
僕もすぐに彼女の左隣に腰掛ける。
「何飲む?」
「なんでもいい」
彼女はカウンターにいる男性を呼び出し、注文した。
「若いマスターだね」
「あら、そう?」
「だって、大概こういう場所って白髭のおじさんじゃない?」
彼女はまた手で口元を隠しながら笑った。
きっと癖だろう。