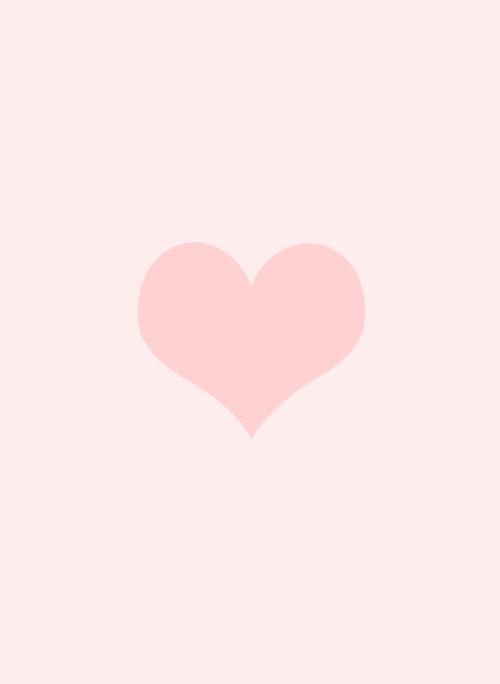「幸せものだな、お前は」
小学校からの幼馴染であり、
僕の一応?親友と呼ばれる立ち位置にも
なっている関口 陸人は唐突に口を開く。
僕は、唇で挟んでいた煙草を遠ざけ、
溜め込んでいた煙を吐き出し、
一息ついてから「どうして?」とだけ
返した。
「どうしてって、お前…あそこまで
非の打ち所がないくらい綺麗で、
気品も良くて、周りへの配慮も怠らない
お嬢さんを嫁に貰えるからに
決まっているだろ?」
「…それがどうして、
幸せということにつながるのさ?」
「そんなこと、わざわざ口に出さなく
たってわかるだろ?」
「…」
僕は少しの間、黙ってしまっていた。
友人の言いたいことはわかる。
しかし、とても現状が幸せなのかと
問われてしまうと素直にはい、と返事が
できない自分もいたのだ。
小学校からの幼馴染であり、
僕の一応?親友と呼ばれる立ち位置にも
なっている関口 陸人は唐突に口を開く。
僕は、唇で挟んでいた煙草を遠ざけ、
溜め込んでいた煙を吐き出し、
一息ついてから「どうして?」とだけ
返した。
「どうしてって、お前…あそこまで
非の打ち所がないくらい綺麗で、
気品も良くて、周りへの配慮も怠らない
お嬢さんを嫁に貰えるからに
決まっているだろ?」
「…それがどうして、
幸せということにつながるのさ?」
「そんなこと、わざわざ口に出さなく
たってわかるだろ?」
「…」
僕は少しの間、黙ってしまっていた。
友人の言いたいことはわかる。
しかし、とても現状が幸せなのかと
問われてしまうと素直にはい、と返事が
できない自分もいたのだ。