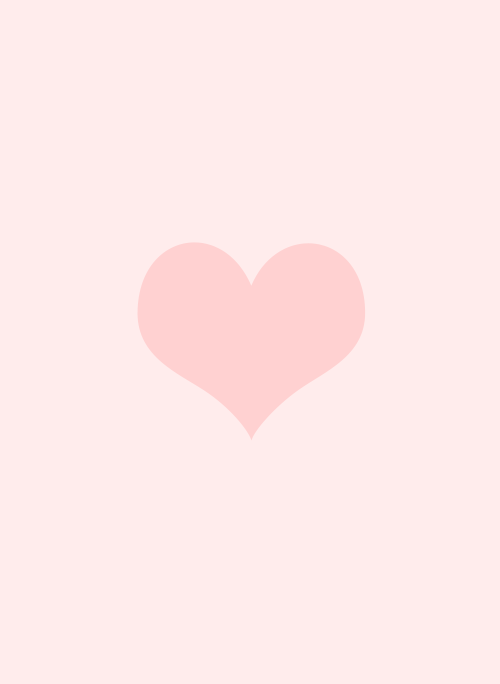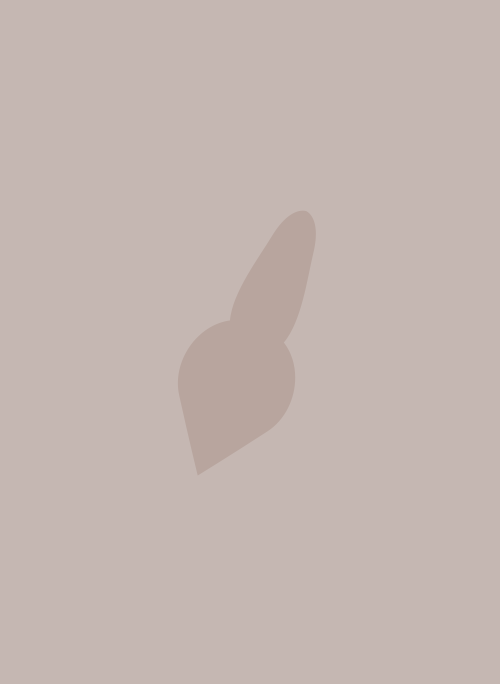手足にはこの前購入したと思われるロープできつく縛られている。
かろうじて口元だけは何もされていないが、これではろくに身動きもとれない。
「なんでこんなこと……」
ぽつりと呟くと田中くんは目をすっと細めた。
「なんでって?
愛しい人を傍に置いておくのにいちいち理由がないといけないわけ?」
「それにしても限度ってものが――……っ」
首筋に当てられた冷たいものに息を呑む。
それは首筋の皮膚を、まるで楽しんでいるかのように、なめらかに滑っていく。
ぴりっと痛みが走り、そこからじわりと血が出てくるのがわかる。
「やっと……やっと手に入れたんだ……」
「田中くん……?どうし、――っ!」
田中くんは唇を噛み締め、制服のリボンに手を伸ばす。
それはブチっと音を立てて引きちぎられてしまった。