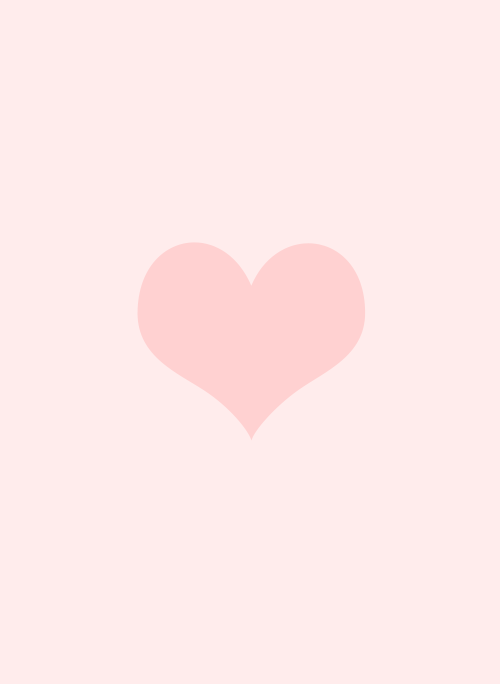***
「(ほら、今日も)」
僕の視線の先にいるのは、いつものようにフェンスに手を掛けて外を眺める君。屋上を一段上った場所にいる僕は、それを毎日見ている。君はいつもいつも、そこにいる。
そうしているときの君と話したことは無い。ずっとこうして見ているだけ。それでも、いいと思う。愁いを帯びた哀しそうな瞳でどこか遠くを眺める君は、触れたら消えてしまいそうだ。
かたり、と君は音を立ててフェンスから手を離す。そしてフェンスに寄りかかり、俯いて瞳を閉じる。その君の横顔を、僕はじっと見つめる。
かしゃん、とフェンスが音を立てた。ずるずると引きずられるように床に座り込む君は、抱えた膝の間に顔を埋める。僕は動かずに、それをただ眺める。
僕の耳に届く、君の嗚咽。静かなこの場を切り裂くその声は、まっすぐに、僕の胸へと突き刺さる。僕と君しかいない屋上に響くその声は、――――一体誰のために流されているのか。
しばらくの間そうしていた君は泣き止んだのか、徐に立ち上がると屋上からいなくなる。それを見送って、僕は君がいたところから君が見ていた景色を眺めてみる。
蒼い空と、僕の住む町の風景。真下を見下ろせば、色とりどりの花が咲き乱れている。それからふいっと視線を逸らし、僕は君の出て行った屋上の扉に視線を合わせた。
君を追いかけるようにして屋上を出る。そのまま階段を下り、出たのは教室棟。授業中であるため廊下には誰もいなくて、君はきっと保健室にでも行ったのだろうと検討をつける。保健室に向かおうと、足を踏み出した。
――――と。
足音が聞こえる。咄嗟に近くの空き教室に飛び込んで身を隠す。幸い通った教師は気付かなかったようで、僕はほっと胸を撫で下ろした。同時に、チャイムが校舎中に鳴り響く。騒がしくなってきた廊下を、生徒と生徒の間をすり抜けて歩く。いつの間にか身につけていたこの技は、意外と便利だと思う。
君を探して校舎を移動する。しかし、辿り着いた保健室にはいない。どうしようか、迷った僕は屋上に戻ることにする。