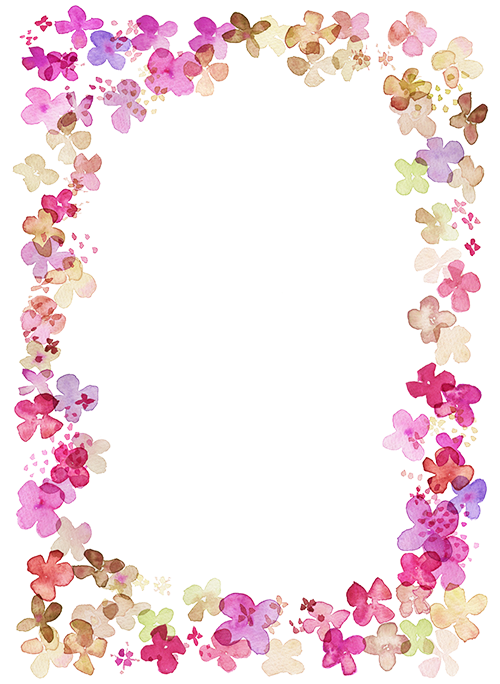「……」
うそ…。
蒼が私を好きだなんて…。
言葉に詰まる。
からかわないで…。
そう、言おうとしても、蒼の目は有無を言わせない真剣さがあった。
「言っとくけど、おまえの『好き』なんかじゃないからな」
重みを感じたかと思うと、ソファの上に押し倒された。
「おまえのこと、いつもどういう目で見てたか知らないだろ。
教えてやろうか?
ガキのおまえには、刺激が強すぎかもしれないけど」
Tシャツの上から腰を撫でられる…。
「俺の『好き』はこういう意味の『好き』だ、って』
「…っ」
その手の硬さに、熱さに、私は悲鳴に近い声を発した。
「やめてよ…っ」
「やめない」
「こんなの…ヤだよ…っ」
無表情だった蒼の顔が、一瞬ゆがんだ。