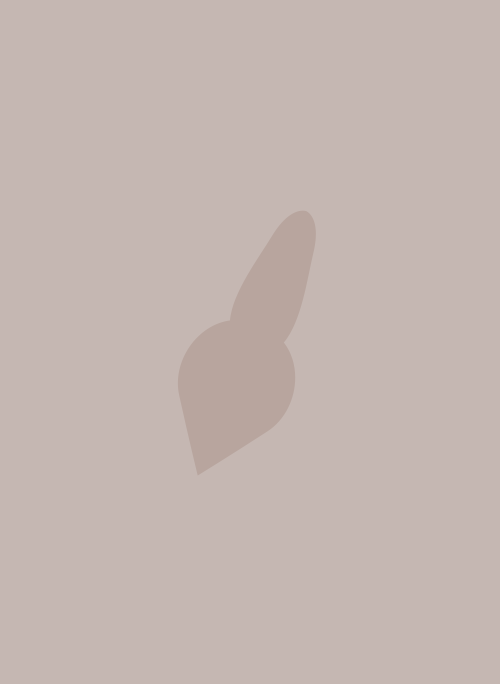士郎は3日後、再び孔明の屋敷を訪れた。
「閣下、北伐参陣の話ですが、お受け致しますが、それには条件がございます。」
「おお、有難い。して、その条件とは?」
「先年の最初の北伐の時に魏延殿が献策した子午道からの侵攻作戦を取り上げて頂きたくお願いします。」
「なんと、それは何故じゃ?」
「我々の歴史では閣下がいつもの祁山から出て、五丈原で対峙されている時にお亡くなりあそばされております。だからいつもの祁山からの作戦ではお亡くなりはしませんが対峙状態になり持久戦が必定。例え、五丈原でなくても、副都長安の前にはビ城があり、そこを抜くにはまた攻城戦になり、対峙が必死。ならば、子午道を通り、直接漢中から長安を突いてはいかがかと。」
当時 蜀から魏を攻める場合は秦嶺山脈を超えて行かなければならなかった。孔明は、祁山からの道、俗に言う関山道を通って、毎回攻めていた。関山道は迂回ルートにはなるが道は平坦で大軍の移動には適していた。ただ、そのルートばかりから来るので、最後の北伐では司馬懿に再三動きを読まれていたという事実があったのである。
「閣下、北伐参陣の話ですが、お受け致しますが、それには条件がございます。」
「おお、有難い。して、その条件とは?」
「先年の最初の北伐の時に魏延殿が献策した子午道からの侵攻作戦を取り上げて頂きたくお願いします。」
「なんと、それは何故じゃ?」
「我々の歴史では閣下がいつもの祁山から出て、五丈原で対峙されている時にお亡くなりあそばされております。だからいつもの祁山からの作戦ではお亡くなりはしませんが対峙状態になり持久戦が必定。例え、五丈原でなくても、副都長安の前にはビ城があり、そこを抜くにはまた攻城戦になり、対峙が必死。ならば、子午道を通り、直接漢中から長安を突いてはいかがかと。」
当時 蜀から魏を攻める場合は秦嶺山脈を超えて行かなければならなかった。孔明は、祁山からの道、俗に言う関山道を通って、毎回攻めていた。関山道は迂回ルートにはなるが道は平坦で大軍の移動には適していた。ただ、そのルートばかりから来るので、最後の北伐では司馬懿に再三動きを読まれていたという事実があったのである。