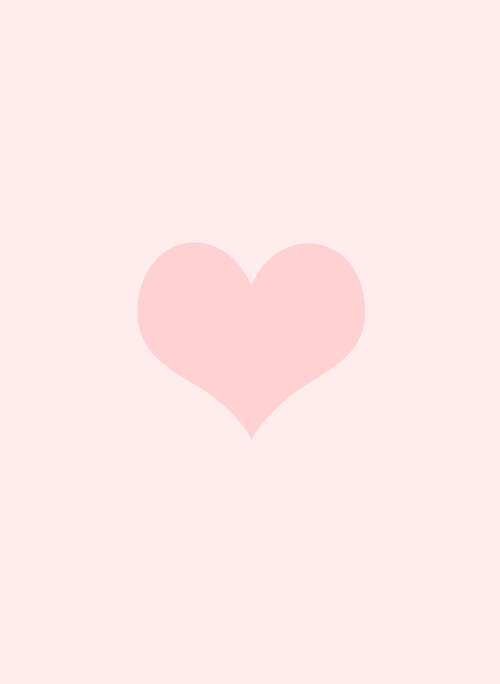「うそ……父さんったら、そんな前から私と一輝を結婚させようとしてたの?」
「あぁ、でも、それには条件があるって言われた。吉美田家の婿養子になる事。これだけは、何があっても譲れないってな」
呆れた……私を勝手に押し付ける様な事言っといて、婿に入れだなんてよく言えたものだ。
「それで、一輝はなんて答えたの?」
「婿養子になるって言った」
「はぁ?私の事何も知らないのに?父さんも父さんだけど、一輝もどうかしてるよ」
開いた口が塞がらないとは正しくこの事だ。呆れて窓の外に視線を向けると、一輝の「そうじゃない」って声が微かに聞こえた。
「親父さんは知ってたんだよ。俺がホタルを好きだって事を……」
「えっ?」
「確かに、ホタルとは話しもした事なかった。でもな、俺は2年間、お前を見続けてきたんだ。
店の奥を覗くと外からでも居間が見えるだろ?毎日、惣菜屋に行って、居間を覗くとホタルが居た。テレビを観ながらバカ笑いしてたり、親父さんと喧嘩して怒ってたり、大口開けて寝てる時もあった」
ゲッ!そんな姿見られてたなんて全然知らなかったんだけど……
「いつからか、そんなホタルを見るのが俺の楽しみになってたんだ。笑ってるホタルを見ると、今日はいい日だなって思う様になって……
だからお前と結婚する事になんの抵抗もなかった。むしろ俺にもやっと家族が出来るんだって嬉しかったよ」
「一輝……」
車窓から差し込む西日が、寂しげな一輝の横顔を朱色に染めていく―――